

斜 陽
密雲衝いて戦闘機が現れた。見る間に二十数機が急降下したと思うと、
ダダ…ダダ…。
私は思わず防空ごうに飛び込んだ。その上へ折重なるように二人三人・・・・・。側の窓ガラスがグラグラと破れた。物すごい爆撃である。私は両手で耳を防ぎ、頭を両足の間へはさんでじっとすくんでいた。
爆撃は瞬間的で飛行機は南西方面へ飛び去った。一息ついてごう外へ出ると、
「地獄の一丁目だったな」
「シャバをさらばしたようだったよ」
などといって自分の顔をつねってみた。
我が身の無事を祈って互いに過去への笑い草となっていた。でもあちらこちらで子供の泣声や悲鳴がひとしお哀れをそそった。
漸く黄昏。夕雲を真赤に染めた向こうの火炎がえん魔やよう鬼のように燃えている。そして大満州の牡丹江市は最後のあえぎに戦(おのの)いている。
それは昭和二十年八月十三日の午後四時過ぎであった。私は牡丹江駅の配車やら北満地区から引揚げて来る避難民の整理やら世話のため光雲橋を渡って太平路へ出た。
ふと駅構内を見ると爆撃の後が生々しい。
レールがあめのように曲がっているもの、屋根を抜いているもの、機関車が転覆して火を吐いているもの……。そのすぐ横には真黒になった死体が五ツ六ツ転がっている。腕のないものや首が切れて胴が逆につっ立っているものなど急に修羅場と化してしまった。あたりには阿鼻叫喚とどうこくに眼をおおうばかりの惨状を呈していた。太平路に出ると市内警備隊が右往左往している。東満第一を誇ったあの並木路も爆風で倒れ硝煙がうずまいて血なまぐさい。私は戦場の凄惨さとなぜ戦わねばならないかという疑問から何か矛盾性を発見したように思われた。
関東軍司令部は延吉へ撤退したとかで命令系統がなく、第五軍へ兵器受領にいった沖中佐は、帰って五人に一銃しかない貧弱さに唖然とし関東軍終えんの様相を暴露したといって慨嘆落涙していた。
「徒手空拳でもいい、最後まで戦いましょう」
私は沖中佐に言った。
「われわれの死が近づきつつあるのだ…。あの煙を見ろ、満鉄工場も軍人会館も灰じんに帰した」
沖中佐の指さす西の空を二人で望んだ。
「ああ!」
私は思わず凝視した。沖中佐も私の顔を一べつして空をあおぐと高度千米位の飛行機がまたこちらへ近づいて来る。それが木の葉のように変幻して飛ぶさまは、高射砲を警戒しているように思われた。
やがて急降下の体勢をとるや友軍の対空砲火が火を吐いた。断末魔の十字砲火ともいうべき凄しい砲撃である。われわれも全身に勇魂がみなぎった。と見る間に数機の中一機が墜落している。沖中佐の顔がゆがんだかと思うと、
「ざまあ見ろ」
しかと軍刀を握っていた。
大陸の野に暮色がかかるころ、漸く陽は西に入り大地の肌を流れるうすら寒い風は静寂を取りもどすかのように心を誘った。黄昏は美しい。
大陸の地平線が画線を描いてミレーの晩鐘が去来するようだ。戦場を忘れたように小虫が鳴き始めた。駅前は避難民が親を求め子を捜してざわめき、燈火管制下に列車の汽笛のみが耳架(だ)を打つ。南の丘には貨物しようが連なり軽いスロープが眉墨をひいたように黄昏に浮彫されている。私は平静をやや取りもどしたので停車場司令部で沖中佐に会い虎林、東寧方面より南下する避難民を収容する配車について連絡した。
私は牡丹江兵事部の分乗車輌を依頼し、明朝七時二十五分発を約して停車場をあとにして、官舎へ帰ったのが午後十時四十分。
それから携行品と残しておく物品を区分して整理した。ラジオをこわし、アルバムに火を点け過去の一切を忘れようとつとめた。まぶたに映ずる若き日の群像…。童心が戯々と遊ぶわすれな草…。
死 体
昨夜はよく眠った。何もかも忘れたように眠った。二重ガラスにしずくが流れて朝陽に輝いている。ペチカの上にクモが巣を作ってほのかに揺れている。どこかで鳥がないた。
私はそっと小窓を開けて街の表情を眺めた。新市街に通ずる大通りには、朝早くから朝鮮人が西の山へ避難する姿が目立つ。星輝中学と牡丹江中学の学生連が木銃を持って、裏山の方へ行進して行った。昨日の爆撃など忘れたような朝の風景である。
小窓を閉じて夜具を上げると、
「おい!起きたか」
益村君の声。ちょっとメイテイしているらしい。言葉が濁っている。
「お早よう・・・・・。なぁんだ、朝から景気がいいな、水サカヅキが過ぎたのだな」
「何?水サカヅキ・・・・・。縁起でもない、一杯飲まねえか、勝利の前祝いだ、なぁ塩原」
塩原君の姿が見えないのに、彼は大分酔歩がジグザグなので言葉も迷言をはいている。
私は独身者益村君の他愛ない姿に戦争など忘れてしまった。
「益村・・・・・お前、銀座の道ちゃんに別れて来たのか、もう明日と知れぬ命だぞ」
彼と二人で、よく通った銀座通り「ゴンドラ」の通子さんのことを思い出してプッとふき出した。
益村君は右手の酒ビンをラッパの格好でグーと飲めは、
「道ちゃんとは道ならぬ恋さ・・・・・。なぁトン馬」
「トン馬?」
「トン馬だよ・・・・・。酒も飲めねえ御仁はトン馬だよ」
「そうか」
私は、酔客益村君は北海道の産で、その昔アイヌの娘と恋の逃避行をしたというロマンス?を思い出して、おかしくて言葉が続かなかった。その時である。
「ダダー‥」
機関銃の音が木霊(こだま)した。それは光雲橋南詰にある特務機関の屋上から火をふいた。
飛行機だ・・・・・と私は直感した。しかしそれらしき姿は見えない。機関銃の射撃と平行して街がざわめき出し、あちこちに怒気や人を呼ぶ声が耳架(じだ)を打つ。
「何かあったのですか?」
私は巻脚はん巻くが早いか戸外に飛び出して尋ねた。その人は青年学校の教師らしい。
「エキ河に戦車が来たそうです」
「戦車が?」
「エキ河の橋は日本軍の工兵隊が爆破したので恐らく渡河出来ないでしょう」
教師は殺気立って語調が震えていた。それで特務機関から威嚇射撃をやったことが読めた。私は兵車部の全職員に伝達しなければならないと決心した。そしてすぐさま官舎街を大呼して回った。
「それ早く退避しろ」
隣の六ツになる吉良幸子ちゃんを抱いて、兵車部の乗用車に積み、本通りへ出た。
「お−い早く駅まで行かねば、女子供は危険だぞ」
私は、妻を蹴飛ばすように自動車へ押込み、翁長さんの運転で幾往復も駅へ運んだ。
「駅が爆撃されたら南下出来ないぞ」
私は皆んなを励ました。
「今日中に拉古(らこ)まで行き、今夜一面波(いいめんば)まで南下しないと戦車が来るぞ・・・・・。来ればひとたまりもない、早く早く」
最後の家族を運び終わると虎林から避難列車がホームに滑り込んだ。私はその列車を見て眼頭が急に熱くなった。それは弾丸に列車の腹部を射抜かれているからだった。
奉天まで南下しなければならないこの列車を見て、前途には多くの難関が横たわっていることを予想して、身体の硬直するのを覚えた。
家族を三番ホームに集めて、途中のことや子供の処置などを注意して、貨車の中をのぞいた。
「あ!」
私は直視出来なかった。
貨車の中には死体が累々と積まれ、板の間からは血のしずくが落ちているではないか…
出 発
夏といっても、大陸の朝は冷たい。万物まだ眠りから覚めやらぬ大平原。まさに活動せんとする植物の精、変幻極りない地上の葛藤に人生はあまりにも無情である。
われわれは出発の準備に余念がない。今日こそは戦車が来るであろうと予期して一同の魂は燃えた。
「君達は速やかに南下して、関東軍司令部と合流してくれ、その途中には幾多の苦難忍従があると思うが、断固克服して初心を貫き無事故国へ帰るよう祈っている。私はこの地に踏みとどまり…」
兵事部員に挨拶する部長豊浦大佐の声はちょっととぎれた。居並ぶ三十余名の者には、その苦悩が読みとれた。そして頭を垂れた。「君達の後を追って行く決心であるが、事態が緊迫している折、あるいはこれが最後の対面となるかも分からない」
と言葉を続けて北の空を仰いだ。
大佐のほほに流れるひとしずく。一同は一瞬沈黙に閉ざされた時正に四時。準備された最後のきょう宴、別れのさかずきが取交わされわれわれの前途に幸あれかしと祈った。
さかずきが重なるにつれ、興奮もやわらぎあちこちで談笑が聞こえ、大佐の破顔も見られた。
「あの官舎を捨てるのは惜しいなぁ」
物持ちの岩滝君が感慨無量。
「出発のときには火を点けるのだ…。灰にして出発しようじゃないか」
独身者の大久保君が一同をへいげいしながら叫んだ。
「それじゃどこから先ず火を点ける」
「知れたことよ、南の果てからだ」
「南の端は岩滝君の家じゃないか」
「仕方ない、どうせ焼けるのだ。今日の南風は強いぞ」
そろそろ出発が迫った。
「では八百屋お七にはだれがなる?」
「お七?」
「火点け役だぞ」
「お七の身代りはおれがやる」
無一文の益村君と衣しょう道楽の岩滝君がしきりに張合っている。
「さあ出発だ!」
一同はさかずきを置いて立った。
「元気にやるんだぞ…。命を粗末にするな」
「うむ!命か…。そうだなぁ」
南下組の二十名と残留組の十数名が硬い握手を交わして、わが家を後に新市街を通り、徒歩で郊外に出た。
なまぐさい南風がすずろ顔をなぶる。混乱した街の様相から脱して、何もかも忘れたように一歩一歩南を指して…。
貨物しようのスロープにかかれば焼跡が右に、煙っている屋根が左に、遠くには満州航空株式会社の黒い煙、牡丹江最後の姿は余りにも哀れである。行き交う市民の群や、全財産を一頭の馬にたくして親子三人が南下するもの…。トラックに全社員を乗せて下る満州拓殖株式会社の従業員などが朝日に照りはえて、拉古街道をうずめている。われわれはやや空腹を感じたので丘の上で小憩した。携帯口糧は乾パンだ。一望魔の海の様に活気がない、そして北方から来る列車とてない。
私は二、三年前虎林虎頭方面で駐屯した記憶を呼びもどした。国境地区は今ごろ激戦しているかも知れぬ…。兵舎は砲弾の雨に見舞われているに違いない…、と思った。
三十分位休んで牡丹江市に名残を告げ再び足を運んだ。
(落武者落武者!なんて情けない態だ!軍の司令機関はどうしているのだ!祖国はどうなっているのだ!われわれの命は何時まで続くのだ)
交錯する色んなことが自分で自分をしかるようにわいて来る。道路は乾燥して一陣の風に、大きい旋風を巻いて黄じんが飛ぶ。
避難民は陸続して南下して行く。丘のふもとを右折左折して拉古の丘営近くまで来た。すると後を追って来た一台の乗用車が私の前で止まった。
戦火の夜
私は眼をみはった。赤ん坊の胸を射たれているものや、頭部が砕けて血をふいているもの・・・・・。
無コウの民の霊に恭しく頭を垂れた。
ぁちこちの不幸を目の前に見て、とうとう声を立てて泣き出すもらい泣き・・・・・。
若い母が、子供の死体に取りすがり何時までも泣き叫んでいるさまはひとしお涙をそそった。そしてある興農合作社の若き婦人は生々しい戦慄の跡をこのように語った。
「列車が、林口を過ぎたころ転寝(うたたね)から目覚めてふと北の空を仰いだ時、各車輌がとても騒々しかった。
それで私はどうしたのかと思って半ば焦燥と半信半疑を抱いて再び窓から上半身を出した、するとどうでしょう…。百メートル位の至近距離に飛行機が現れて列車を追っているのです。私は瞬間死を直感したその時です。物凄い機銃の掃射が聞こえたかと思うと異様な音をたてて車内に弾丸が落ち弾痕が人を射た。車内は騒然としていきり立った。私は思わず腰掛けの下へもぐり込んだ。そしてじっとすくんだ」
その間二分間程度である。
飛行機は三回位旋回して掃射したが、やがて北西の雲間に消えて行った。ほっと胸を撫で下ろすと列車がとまった。
もう程なく液河に近い河の畔だ。
「ああ私はもう正視出来ない・・。無惨な死体、泣き叫ぶ声・・。阿鼻叫喚という言葉は、こんな場合のために作られた言葉であろうか、私はもう…」続く言葉は消えて語尾が濁った。牡丹江駅に時ならぬ哀惜の空気がみなぎり、やがて警備隊員が死体の整理を始め、トラックに積んで第五軍司令部の裏山へ運んで行った。もう程なく列車は出発だ。プラットホームには水筒を片手に水を求めている者、半狂乱になって子供を捜している母の姿、駅長が早く早くといって窓から押込んでいる発車前の混乱。
またしても入日が中天を赤く染めて、夜気が忍びやかに迫ってきた。
列車は汽笛一声・・・・・。暗闇を衝いて牡丹江を離れた。何分にも我が軍の貧弱な火器と兵員の寡少でちょう戦するのは不可能である。ソ連は軍火器や機械化部隊をもって標ぼうしているのだ。私達が幼い頃コザツク騎兵の勇壮な突進ぶりを小説、実話でよく聞かされた。今その機械化と空拳が相対している。そして世界大戦のルツボに追込まれているのである。
列車は悲哀を乗せて一気に南下した。
私は家族一同三十余名を出発させてほっと安どの胸を撫で下ろした。もうとっぷり暮れて墨を流したようなヤミ夜になった。満鉄工場は未だ燃えている。貨物しように火が点いたアンペラらしき ものがメラメラと燃えて丘の上がぐれんの炎と化してしまった。その時…。
南の空に大砲の音に似た爆発音が聞こえた0すると天を沖するばかりの大火となって夕空に反射しこちらまで明るい。
「あれは満州航空会社だ!」
「またドラムカンが爆発した!」
次々にさく裂するガソリン…。さながら煙火のきょう宴の様だ、牡丹江市の断末魔が近づいて来た。
今朝エキ河付近に敵の戦車が来襲したというのは、いささか信じ切れない…とこんなことを独りで思いながら私は夜道をたどつて新市街に出ると、
「だれだ!」
不意の言葉に虚を衝かれた。
「はあ…。牡丹江兵事部の者です」
といって尋問の主を見すかしたところ、特務機関の物々しい武装振りが淡く網膜に映じた。
「よし−空襲警報中は夜道を歩くのじゃない」
しかるようにいって光雲橋の方へ去っていった。新市街の並木路が夜の南風にサラサラと音を立てて一葉がほほをなぶった。
漸く官舎へたどりつくと、
「君!早く帰らないか…。明朝四時出発だぞ!」
とせき込むように益村君の声。
大地のはて
翁長君が運転している。彼は何時もにこにこして愛きょう者である沖縄県の産。運転手である。
「官舎は燃えているぞ!」
「そうか!やったか!」
私は驚きと共にいちまつの哀愁を感じた。住みなれた官舎が焼けたのだ。翁長君はハンドルを押
つ
さえて煙草に火を点けながら、
「新市街の満鉄社宅も燃えていたよなぁ、もう牡丹江もさらばだ」
次々に焼失していく牡丹江市東浦第一の都も焦土と化してしまうのだ。
お互いにじんあいに汚れた顔を見つめながら、
「その自動車どうするのだ」
リーダーの土橋氏が尋ねた、
「行ける処まで行くさ・・・・・。なぁ益村」
カン詰のふたを切る益村君がびっくりしたように翁長君を見つめた。
「牛カンだ、食わないか、その代わり乗せろよ」
翁長君は面白い奴だといいたいような顔をして胸いっぱいの紫煙をはいた。またじんあいが巻いた。
凄い南風だ。
その間絶えず行き交わすトラック…。乗せてくれと叫ぶ北満らしき避難民…。足をひきずりながら歩く開拓団の子供…。
行方定めぬ果てなき旅路は南へ南へと続いて行く。拉古の駅近くまで来ると、もう日が西山に落ち、ねぐらへ帰る雁の鳴き声のみが耳を打つ、ここまで来れば牡丹江も分からない。一望千里の東満が拓けて地平線に消えている。
翁長君が南下列車がもう一回来るだろうというので一同は、拉古駅で待つことにした。
西の空に妄星が輝いている。そしてレールが白く光って南北に伸び大きくう回している。拉古駅には五十名程度の避難民が列車を待ち、ざわめきが暮色の中にただよう。向こうで放馬のいななきが聞こえた。
「来るでしょうかね」
見知らぬおばあさんに聞かれた。
「間もなく来ますよ‥・。混んでいるかも知れませんから危ないですよ」
私はこんな場合女、子供、老人は無理だと思った。列車を待っているといやに寒気がする。
「日暮れて道遠しだ」
だれかがつぶやいた。
「ままよ」
またため息。星が瞬き周囲が尺度を弁ずることが出来ない位暗くなると、
ゴーゴー
「うわあ−」
雪崩の如くホームいっぱいになった。
「危ないから下がって下さい!」
駅長らしき人が怒鳴っている。その瞬間列車はホームに入った。列車のゴングがやみに響く。
「それ!」
潮のように列車に窓に押し合う。たちまち鈴なりになった。私はどうしても乗らなければならぬと連結台のところまでかき分けた。列車は汽笛も鳴らさず始動した。
私はホツと胸を撫で下ろしたが、足場が危ないので気が気でない。時々満員の波が押寄せてヒヤッとする。右手はデッキに左手は幌につかまえているものの軍刀がブラブラして気持ちが悪い。
「よく乗れましたな。危ないですよ、もうちょっとこちらへ寄りなさい。そうそう」
側にいる長ひげ男。案外やさしい人だナと思い、
「すみません」
感謝して右へ寄ったが、手がしびれて睡魔が襲って来た。夜風が楓々と吹いてうすら寒い。
列車は山腹を走っているかと思えば鉄橋を過ぎ、下の濁流を見ては現実の思いも失せて冷水三斗。
悲喜交々を乗せてひた走りに走る避難列車。私は身体の自由を失ったので思い切り人の中にくぐつた。するとすぐ隣を見て叫んだ。
「あっ!この人死んでる!」
死体を抱いて
異様な叫びを聞いた私はギョツとした。周囲の人は皆その言葉に耳をそば立てた。
将校だ。栽は肩章の大尉を見て日本軍将校と直感した。左手を軍刀のさやに右手は垂れて眼が散大している。私はすばやく左手の脈はくをみた。鼓動がない。脈もない。
「さっきまで話していましたよ、この人は」
協和服の男がいった。
「東寧の歩兵部隊の中隊長とかで全滅になった時、丁度南下列車にたどりついて乗ったとか言っていましたがね」
その男はなおも言葉を続けて、
「部下にすまない・・・・・といって合掌していましたよ。何しろ国境はひどかったですからなぁ」
列車の音と共に当時のことを呼び起こすようにいった。あたりは無言で感に打たれたようになったので、
「そうですか‥・。それじゃこの列車は東寧から来たのですね」
私は、死んだ将校の身体を支えながらこう言った。死人は重い、自分の身体さえ持ちあぐんでいる時に死人まで重みが加わっては、もうたまらない。死人の顔は蒼白だ。星の光に青くなっている。
この責任感の強い大尉の故郷へ知らせたいと思って胸のポケットヘ手をやったところ、
「血だ!」
思わず叫んだ。口から血のようなものが流れている。それが胸を伝って私の右足へ落ちた。
列車はひた走りに疾走する。やがて横道河子が近づいた。私は列車が止まれば駅員に死体を頼もうかと思った。だがしかし停車時間が短いためと混雑のため下ろすことは出来なかった。
私は眠くなったので死体を抱えながら連結台の幌に寄りかかった。死体は冷たくなって来た、だがしかし…・・。私は心よい眠りのベールに閉ざされた。列車の騒音が子守歌となって小刻みに消えて行く…。
ふと目覚めた時にはゆるやかな坂をあえいでいる。そして山の中だ。少し霧がある。
朝五時半ごろであろうか東雲が朝日に輝き、列車の窓に朝露が光っている。
「朝だ!」
立並ぶ白樺の林を縫って詩情豊かだ。昨夜中死体を抱いていたので非常に重いように感じた。どこかで停車でもすれば死体を埋葬しようと思った。
列車は依然霧の中をあえいで行く。
横道河子を過ぎた山中で駅もないのに列車は停った。すぐ傍らに小屋がある。満人が飽子(ぽうず)を売りにきた。乗客は窓を解放して飽子を呼ぶ。私は死体を下ろして駅員に処理を頼んだ。
工キゾティック
幾度か戦火をあびて一面波(いいめんば)へ到着した。
列車は給水や石炭積載をやり同胞は環境の整理などに余念がない。向うではごうを掘って死体を埋めている。可愛い子供の死顔に、そっと薄化粧をしているお母さんもいた。子供に泣きくづれる母性愛、死んだ子供を背負って離さない、一面波の駅は戦争の悲劇にあふれた。
「おお無事か」
自動車を運転していたはずの翁長君が一面波に着いている。
「自動車はどうしたんだ?」
私は乾パンをかじりながら尋ねた。
「河の中さ・・・・・寧安の河の中で座っているよ・・・・・熱いからなぁ」
翁長君は相変らずのんきだ。三十分位停車した列車は間もなく発車することになった。
「また弾の洗礼だ…・でも今度は列車の最後尾に機関砲をすえてあるから大丈夫だよ」
と軍人が話合っている。やがて列車は大平原へ出た。人家がある。五常を過ぎた頃は、旅の疲れもいえて、何か期待にはずむ興奮にかられた。そして単調な車輪がリズムカルな感じをもたらした。
平旦な大陸には、あちこちに煙突も見え、ビール工場などの煙突が櫛比(しつび)している。
ほどなくハルピンである。
ハルピン駅構内へ入った。大ハルピンだ−−。
人びとは無事虎口を逃れて、目的地ハルピンに到着したのだ。
駅構内には大型機関車のゴングが入り乱れている。駅向こうにはハルピン特有の森が見え、遠く緑樹繁る中央寺院やオリエンタルホテルの豪壮なビルが眼に入る。
私はハルピンのエキゾティツクな容姿に感を打たれた。戦争などはどこ吹く風とばかりに行き交う馬車。私はこの風物詩大ハルピンを眼前に見て大いなる希望に燃え、前途が明るくなったように感じた。
石だたみが軽いスロープになって中央寺院に登る。北にはキタイスカヤ街が見え、その向こうには松花江がゆったり水をたたえている。
日本人の多い地段街は店舗を閉鎖しているものの、やはり戦前の威容を整えている。
市公省から東へ通ずる南京街も盗人市も皆景気がいい。私は流れ流れて来た過去一両日がばかばかしくなって来た。
「全く無風地帯だ!」
私は思わず心の中で叫んだ。電車は日本人が運転している。
戦争をしているようにも思えないハルピンの姿が終戦と同時にピリオドを告げるとはだれが予期したであろうか…・
八月十四日
われわれはすぐハルピン兵事部の官舎…河溝街まで行った。日本軍のトラックが南から北へ、北から南と物資を運んでいる。
作戦行動がどんなになっているか皆目分からない。私達は長途の旅行から解放されたように独身寮に来た。そして独身寮には、先発したわれわれの家族がいるという知らせに胸が躍如とした。一日の別離が千秋の思いとは、このことかと皆んな会いたくて仕方ないような顔をしている。
(無事でいてくれよ・・・・・)
と祈る心を圧えて寮の門を潜った。一行二十名。かいごうだ−皆んなうれし泣きに泣いていた。
無事を喜ぶ二人の魂……人生の俗悪を忘却した美しい愛情の発露である。
やがて互いに旅程を語り合い打ち寛ぐ高らかな笑いがあちこちに聞えた。
軍酒保から放出したビール、酒、米が運ばれる。そして美食三昧のだいご味にひたる。
私は牡丹江の大火災や列車の阿修羅の悲壮を皆んなに告げた。そしてその時友軍の飛行機が大きく旋回して去った。
(ああ、われわれはハルピンに来たのだ)
家族と会ったのも束の間、すぐ南下させた。一客車貸切って、食糧を積み一路南を指して奉天へ…
明日は天皇陛下の重大放送があるという街の話題に、捨鉢的な兵隊の気持と市民の不安が街にうず巻いていたように思えた。
然し・・・・・街に往来する重火器、トラック・・・・・は戦争が眼前に迫っているような予感をそそる。
私は軍刀一本のみを頼りに、夜を徹してよう撃することを決意した。上司の命令はなく、ただ守備隊より刻々と報せて来る戦況。
もう松花江を渡った・・・・・戦車が市中に突入した・・・・・あらぬ流言が人から人へ伝わる。
駅前にトーチカが築かれ、辻には土のうが積まれた。重要市街は鉄線が張回されて、一歩も通行出来ない。
私は、故郷に向かって祈った。一行十数名は最後の杯を交した。
憲兵大尉の自殺
「今宵限りの命とははかないものだ・・・・・」
街はやや静寂を取りもどした。守備位置についたのだ。どこかで犬の泣き声。
遠くに砲声が轟いた。空の局部がパツと明るくなると爆破らしき音が起きた。
関東軍防疫給水部が爆破したのだ。嵐の前の静けさが二時間ほど続いた。
「闘争なし…現在地において待機…」
静けさを破ってトラックに乗る伝令が走った。
私はやっとむしろに寝転んだ。軍刀を抱えた手は夜気で冷い。やがてわめく声が次第に大きくなって石ダタミを通る兵士二ツ三ツ。
「相手がどこまで来ているか分からないじゃないか。益村君なぁ」
「相手は本能寺にありだ・・・・・慌てることはねえよ」
といって、腰の水筒を傾けている。酒がにおって来た。
「可愛い酒と一緒に死ねば本望だよ」
といって、ニヤニヤ笑っている。
頭上に繁る並木路に露が星明りに光っている。樹木から見える北斗七星。
けんらんたる星座の輝き…私は恍惚としてしばし空を仰いだ、限りなき空間に輝く無数の星のように、ただじっとして不安もなく焦燥もなく、下界を照らす。夜は静かだ。このうつし身にこんなひとときがあったのかと…戦いを忘れて淡いノスタルジヤにかられた。
ふと我にかえると戦友は折り重なるように寝ている。酒豪の益村君はいびきをかいて水筒を抱いている…。
「野郎・・・・・赤垣源蔵そっくりだ」
ひとりつぶやきながら、兵事部の正面を通り香坊へ通ずるメインストリートに出た。
すると電車道路の真中にうごく黒い影。
「はてな・・・・・?」
私はいぶかった。
そして近づいてみた。
「どうしたのですか」
「・・・・・」
「苦しいのですか?」
「うむ・・・・・ウウ・・・・・」
苦しそうである。
「こちらへ来ませんか…さあここは危いですよ」
私は急病だと思って、男の右手を抱えた。
「ああ!」
私はトッサのひらめきに二、三歩後へ退いた。男は軍刀を握っている。そして頭を自分のまたの中
へ、うなだれて立上がる力さえない。
石ダタミには血が流れて真赤に染めている。
(切腹…)
私はがく然とした。このままではひき殺されると思い再び男の両手をとった。
その瞬間男は息絶えてしまった。重い。血が腹から淋りと流れる。青白い顔はまぶたを閉じて数秒前の苦しさは見受けられない、兵事部のランプの下まで引きづって来た私は、この男が電車通で死んだのが不思議でならなかった。そして敗戦による精神的不安から異常を来たしたものかもしれないと思いソッと胸をさぐってみた。するとドツと血が噴き出した。臓腑が見えるではないか。胸のポケットに何か堅いものがある。
私は素早く手にとった。遺書でもない。うす暗いランプの光に「憲兵手帳」という文字が読み取られた。そして裏には「陸軍憲兵大尉西森章一朗」と書いてあった。
敗戦がかもし出した大きい責任問題から自殺し果てたのかもしれない。
夜は更けて行く。淡いガス燈が死体を浮彫するように照らしている。
私は懇ろに大樹の下に安置して合掌した。どこかで鋭い砲声がした。
レールの上には軍刀が青白く光を放っていた。もう十二時ごろであろうか・・・・・。大陸の夜は無気味に更けて行く。
終 戦
ソ軍はとうとう来なかった。明くれば八月十五日ポツダム宣言受諾の天皇放送があり、国を挙げて未曾有の難関に直面した。
われわれは泣いた。異国の空で男泣きに泣いた。将来が真っ暗やみになった。
領事館の表札も外され、軍隊は北飛行場と競馬場で武装解除されることになる指令が飛んだ。市民は進退に迷って街を右往左往する。この大ハルピンは混迷の雲で覆われ、やがて八月二十日・・・・。
ソ軍の入城式があった。先ず飛行機が五機、市内上空を旋回して北へ消えると、間もなく戦車が長々と連なって入って来る。大型の戦車で機械化を誇るソ軍のシンボルでもあった。
油に汚れた歩兵部隊、疲れ切ったスラブ族、モンゴル人、西欧系露人などヒゲの濃いもの赤いもの、日本人より背が低いもの、雑種の混成部隊が示威行進する。
市民は歓迎もせず赤色ソ軍を異様な眼で見た。敗戦の現実を知らないわれわれは聞くもの見るもの驚異であった。
ソ連とはこんな国か、そしてこんな軍隊かと、ただ唖然とするのみであった。
市中行進は長々と続いた。
「チェッ!馬鹿にしあがらあ」
私はあっけない敗戦の姿を、まざまざと見せつけられていささか噴りを感じた。
自動小銃を肩にかけて、油で汚れた軍服を着用しているソ連兵は確かに疲労の色が見られた。ドイツとの戦闘で極度の消耗と忍耐の跡が編隊の全ぼうを見て直感された。
「汚い軍隊だな」
市民の一人がいった。
「見ろよ、レザーの長靴とズック靴の混成だ」
と労働者風の男が微苦笑して思わず右手で口をふさいだ。そしてあたりを警戒してキョロッと眼を流した。
私は幼い時、よくコサック騎兵の突撃隊の勇壮振りを聞かされた。西部劇を思わせるような大地を蹴るコサック。敵地へ突撃する凄しいコサック。今は過去の想い出として、その影もなく機械化をもって装備されている赤軍である。
この入城式に先立ち、市内の大ホテルやビル等は全部接収されて、日本人は終戦と同時に職を失い、市政は赤軍の管理下におかれ、警察権は全然なく、ただソ軍の警備兵が市中を右往左往しているに過ぎなかった。
あちこちのビルの屋上には、ハンマーとくわを形どった赤色旗がひるがえっている。
私達は宿舎へ引揚げた。そして夕食の仕度にとりかかった。
「野山君卵を買って来たから卵飯でも作るか、ああオムレツとかいうやつをな」
大久保君が篭いっぱいの卵を大事そうに炊事場まで運んで来た。
「幾ら買ったの?」
「ウンニャ五十三個だ、三個はおまけだよ」
といって、ニコニコしている。
その時…ソ連の警備兵が来た。五名。自動小銃を持っている。
「おい警備兵だ」
われわれは緊張した。
「国際運輸だぞ、忘れるな」
土橋さんは軍籍を偽るため、牡丹江国際運輸従業員になり切るよう小声で一同に伝達した。警備兵はわれわれが居る階上へ来た。カタカタ靴音だけが異様に響く。
警備兵は全部銃を擬(かく)している。我々は部屋いっぱいに円形にすわった。
通訳らしき白系ロシヤ人が、
「あなた達はどこの方ですか?」
おとなしく聞いた。
「はあ、牡丹江国際運輸の者です」
土橋さんはポロ服を着た白系に答えた。
白系と話している間に警備兵は部屋中を物色している。そしてその一人が今買って来たばかりの卵の篭を提げてゆうゆうと立去るのを見た。
白樺の街
明くれば八月十七日。
敗戦という奈落のドン底にたたき込まれて今や三日が過ぎた。ソ軍が街を往来し白系ロシヤの宣撫工作が目立って来た。その上あちこちにりゃく奪の悲劇を聞かされた。
「僕が秋林百貨店の前を通っていると、人だかりがあるので何事ならんと群衆をかき分けてみると…」
大久保君は煙草を灰ざらに潰して、眼を丸くしながら今日の模様を語った。
「どうだろう、日本人がたおれている。それが無残な最後なのだ」
われわれは動乱の終戦後の情報に餓えていたので、ひざを乗り出して大久保君の顔を見守った。
「拳銃でやられているのだ」
「だれが殺したのだ、ソ軍か?」
「ソ軍がやった。それが日本人の皮長靴ほしさに無理矢理りゃく奪しようとしたのを日本人が抵抗したのだそうだ」
「ひどいやつだ!」
岩滝君がこぶしを握った。
「畜生!」
益村君は歯を食いしばって憤慨した。
「顔を射たれたので、だれだか分からないほどくずれていたよ。全く野蛮なやつだ」
こんな悲劇は市中数多く見られた。夜に入ると銃撃が間断なく聞え、その一発一発ごとに同胞が死んで行くのかと思うと、矢も盾もたまらないほど、血がたぎり立つ思いがした。
うつし身をたえ忍びてぞますらおの今日のいのちを世々に伝えん
私は一句を詠じて敗戦の現実を詠嘆した。
その日その日が恐怖と戦りつと憤怒が巴まんじとなって脳裏に交さくした。ある時は地段術の薬局一家が、全部自殺して放火したことを聞かされて、一刻一刻が暗黒の世界をさまようような感がし、今日まで生き長らえたことが不思議でならなかった。そしてまた夜が来た。
私は、月の光りが入る窓辺に寄って、南に拡がる香坊付近の夜景をながめた。白樺の木がすずろ揺れて葉ずれが鳴る、銃声は間断なく聞えて来る。歩哨が威かくと恐怖のために発射しているのかもしれない。
月が雲間からのぞいて、大地に樹影を投げかけている。時折歩哨が自動銃を背おい中央寺院の方へ歩いて行く。
ソ軍は戦いに疲れて、あらゆる欲望に餓えていた。白系ロシヤ人は、進駐部隊が囚人であるといっていた。ソ軍は囚人部隊を先遣させたらしい。終戦直後の惨劇も無理はない。
夜八時ごろ−チチハル兵事部の坂田少佐夫人が訪れた。
「まあ皆さん、元気な顔して」
四十五歳位の女丈夫とでもいいたいような夫人である。ネッカチーフをとりながら一同の顔を一べつした。
「この間ハルピンに着いた時より、元気そうよ。健康第一で命を大切にするのね」
「今ごろどうしたのです?」
土橋さんは思い出したように尋ねた。
「あのお隣の酒保の女店員のことよ、そのことが気になってね、明日と思ったけれど心配なものだからやってきたの。このごろ娘さんは危くて、きれいな服装しているとすぐ強かんされちゃうわ」
私も、ソ連兵は人前であろうと道路であろうと強かんするという野ばん的な事件はよく聞いていたので、
「そうだ娘さん二人連れて帰るのですか」
「連れて帰ろうと思うんだけど」
坂田夫人は土橋さんの顔を見た。
「今夜は危い、明日にしよう」
さえぎるように土橋さんは右手を振って坂田夫人の言葉を制した。
「おばさん、今夜泊ってやんなさいよ」
寝ていたはずの益村君が頭を上げていった。夜が更けるとも知らず鳩首して相談したが、とうとう坂田夫人と土橋さんと私が泊ってやることになった。外は月光がさえて明るい。
強かん
私は身の毛のよだつ思いがした。坂田さん土橋さんは二階から降り、私も立ち去るよう警備兵から命ぜられた。警備兵の一名は入口に立ち他の二人は家屋内に消えた。われわれは娘の無事を祈りその動静を見守っていた。日本人として救援の術もない。はがゆいがどうしようもない。
ややあって荒々しいソ連語が聞えたと思うと、
「キャア」
絹を裂くような女の声。
われわれの血は逆流した。同胞が暴行されているのだ。
私は思わず拳を握りしめ暴行されているであろう三階の窓を凝視した。カーテンが揺れている。
ガラスが一枚くだけて落ちた。
周りは静かである。満人二、三人が何かささやいて視線がそちらへ向けられている。
やがて五分位経過したであろうか・・・・・警備兵がゆうゆうと立去って行くのを見た。
戦争と強かん、統制のない軍隊こそ、人間が理性を忘れ、野獣と化すのである。
警備兵が帰った時、女店員は出て来た。
頭髪が乱れて、さめざめと泣いている。どうこくだ。これほどの侮辱がこの世にあるであろうか。
ただ泣きくづれて半狂乱となっている哀れさ。
「もう私は帰れない」
私の前まで来て泣きに泣いていた。
私は瞬時の出来事に慰める言葉もしゅん巡して、その真相を聞くことも止めた。
「気を強く持つのだ。この罪は神さまがきっと浄化してくれる…もういい、泣くのは止そう」
私はどうしてなぐさめてよいやら気の毒でたまらなかった。女は危険だ、どこかへ隠さねばならない。天井裏か床下か。
私は彼女二人を床下へ隠すことに決めた、夕タミをとり、座板をめくって、床下に夕タミを敷き、毛布と日用品を入れてやり、少し離れたところに小さい穴を開けた。そしてそこから食事を運ぶことにした。
彼女の戦(おのの)きと不安と焦燥は未だいえない。彼女は朝夕神に祈り合掌して身の安全を祈っていた。
(神よ希(ねがわ)くばこの可れんなる人びとを救い給え)
私も祈った。
それから毎日のように食事を運んでやり、何から何まで世話をしてやった。
彼女達は次第に疲労を忘れ、生への喜びがよみがえった様子で、神の恵みを享受したかに見えた。
この過ちを知った親はどんな思いがするであろうか。私は親という偉大な抱擁力のある無限な慈愛を連想してまぶたを熱くした。
『過失はあらゆる手段によって償うことが出来る』
私は大いなる光明を見出し神の霊感に打たれた。彼女達はもう心配はない。
それから1警備兵は幾度か訪れた。そして財布、時計、万年筆、靴、長靴、皮バンドを強奪して行った。ある警備兵は左腕に数個の時計をつけて珍しそうに得意がっている者もいた。われわれから見れば全くモラルに欠けた低級な、そしてバーバリズムな人種としか思えない。それである日ソ連兵に通訳を通じてこんなことを尋ねてみた。
「君達は何年位教育を受けているのだ」
兵隊は、それに答えず、
「日本人は何年だ?」
あまり問題にもしないような顔つきで聞く。
「十数年だよ…義務教育が六年」
「義務教育?」
「国民だれもが受ける教育だよ」
義務教育ということを解せないらしい。そしてさも不思議そうに、 「ソ連人は十年も勉強すりや、スターリンかモロトフになっているよ」
とカ々大笑する。われわれこそ不可解でならない。鉛筆の形態さえ分からない人種に敗けたとは日本も全く愚かなものだった。
朝ぼらけ
「土橋さん・・・・・いい天気ですよ」
まばゆいような朝日を部屋いっぱいに浴びて、大陸の秋の空気は清々しい。ひげ面を撫でながら横に寝ていたはずの娘達の床に視線をやった土橋氏、
「娘さんはどこへ行ったんだ」
少々昨夜の夢が残っているらしい。
「隣りの李さんの家へ荷物をあずけに行っていますよ、日中はソ連の大泥棒がやって来ますからなぁ」
私は窓から見える李さん・・・・・親日派の李さんの小規模な庭園をながめながら答えた。
無風状態の朝まだき・…あちこちの煙突からは炊煙が真っすぐに立ちのぽっている。
香坊から延びる大平原は地平線に消えて一望千里、北には松花江の流れ豊かに小型蒸気がポカリと浮び、この動乱の地にひとときの平和郷が生れたかのようだった。
李さんは南京街に練布会社を経営する事業家で、戦時中は日本人相手に広く取引していたせいか、終戦後はややもすれば抗日感情に傾く世相を脇目に、とても親切で温情家でわれわれも恩人のように敬服していた。
「皆さん大切なものは私の土蔵の中へかくしておきなさいよ、ソ連人に見られたらひとたまりもありませんよ」
と何かと親切に世話してくれた。李さんは今日も野菜とソーセージを少し持って来てくれた。
「すまないね李さん」
「いいやなぁに、日本人は外へ出たら危いからなぁ、この間も五、六人連れて行かれましたよ。全く乱暴ですソ連人は」
李さんはトルコ帽をかむり満面笑を浮べ、
「戦争が済んで平和になればまた来て下さい。待っていますよハハ」
温厚でらい落肌の李さんは、こう言ってわれわれを元気づけてくれた。私は人情紙風船という言葉は、この世からまっ消されたように思われて感謝した。
私は洗面して部屋へ帰ってみると、娘さんはいなかった。
「朝食たべて来なさいよ、野山君がギョーザを作っているから・・・・・とてもおいしいですよ」
「ギョーザおいしいわね。でも李さんところでご馳走になったわ」
娘二人、この娘の将来は波らんが待ち構えているように思われて哀れでならなかった。
「ヤボンダ、シュダー」
窓下に警備兵の声がした。
背に自動小銃、大きい眼、汚れた黒服、ツンドラ帯に住む特有な感じがまぶたに映じた。
「警備兵だあ!」
「囚人部隊が来た!」
私は娘の処置に苦しんだ。
「三階の屋根裏へ行きなさい。早く!」
娘二人を三階へ上らせて、私は何食わぬ顔をしてゆうゆうと中庭へ下りた。
私が外へ出るや否や一人の警備兵が自動小銃を胸につきつけた。とっさのことで冷汗が背すじを流れた。
そして手を挙げろといっているらしかった。ホールドアツプだ。私が両手を挙げると、も一人の警備兵が服装検査をし始めた。酒気を帯びている。ズボンのバンドを外しポケットから財布を強奪され、鉛筆を不思議そうに眺めていた。鉛筆を知らないのである。とうとう分からないので真二つに折って捨てた。私は無知にあきれ返ってプッとふき出しそうになったのを、くちびるでかみしめてこらえた。ウォッカの臭いが鼻を衝く。
私は両手がだるく辛棒出来ないので頭上で組んだ。すると、
「ウウ・・・・・」
彼らは怒った様子だった。そして、
(娘を出せ娘を案内しろ…)
という風な口ぶりをして、私に自動小銃を再びつきつけた。思わずギョツとした。その時他の警備兵が天井めがけてごう然と威嚇射撃を放った。
「しまった!」
拉 致
坂田さんは、市内の情報に餓えたわれわれにこんなことを言った。
「香坊小学校にいる避難民である将校の奥さんは暴行されようとして、ソ軍の将校を射殺しその場で死刑にされたのよ」
ソ軍は即決である。この奥さんは主人から一丁の拳銃をもらって身の安全を保っていたのだった。
敗戦のため惨めな日本人が一人一人犠牲となって行くたび、哀愁と厳粛な気持に閉ざされて行った。
明日の命がままならないのだ。
ハルピンの街は北満の避難民で寺院、学校、公会堂は満員になり、初冬の厳しい寒さに凍死して行くもの数知れず。その死体は校庭の片隅をごうのように掘って二十人三十人を重ねて埋葬した。
乳のみ児の死体は入十パーセントを占め、後は発しんチフスと栄養失調で尊い命を失ったのである。
瑞穂開拓団、桃山開拓団、高千穂開拓団などは北満から南下途中、満人のりゃく奪と銃殺撲殺で全滅の悲運に遭った。まざまざとその真相が胸にこみあげて来る。
敗戦…何と悲惨な現実であろうか・・・・・。郷土虎林部隊の残留兵士も東安林口間で銃撃に遭ったそうで、鶏寧(ケイネイ)の野戦重砲一ケ連隊は敵に包囲され全滅となったことはあまりにも無残な最後であった。
数々の哀話を残して今また暴行された女店員を坂田さんの手に委ねねばならない。
「そうそう髪も切ったね・・・・・鍋墨をほほに塗って、元気に強く暮すのです」
彼女達二人は、坂田さんに連れられて宿舎を変えて行った。
「色々お世話さまになりました」
と彼女は丁寧に礼を述べた。
「帰国するまではどんな危いことがあっても強く生きるのですよ。この乾パンも持って行きなさい。カン詰も」
出来るだけ持たせてやった。
「あなた達も元気でお帰り下さい。下関ではまたお会い致しましょう。色々ありがとうございました」
見るも痛ましい姿で、河溝街を過ぎ、アカシヤの木蔭に消えて行った。大陸も戦火のうちに夜がやって来た。宵の明星は輝き北斗七星が北にかかって、動乱の下界を照らしている。依然として銃声は絶えない。
明くれば八月三十一日。はや十五日は過ぎソ軍の共産政策も露骨になって来た。先ず正規軍人を戦時捕虜としてソ領に送った。そして産業復興五カ年計画のため労働に従事させた。道路構築、鉄道敷(ふ)設、農耕などノルマを強制させられた。
次に満州内の軍需民需物資の搬送、旧日本人経営の工場施設の撤去が各都市ごとに開始され、労働力にはその土地の日本人を就労させられた。これらの政策が何の布告もなく通達もなく隠密裏に実行されて行った。
(日本人はら致される)
という、うわさが街から街に伝わり、十八歳以上五十歳未満の日本人男子は、警備隊員により強制ら致され、どこへ運ばれるともなく消えて行く。 こんな情報が始まると日本人は一歩も外出する者はなく、屋根裏や床下に潜行するようになった。
われわれはどうせら致せられるものと覚悟を決め、警備兵の来襲に神経をとがらせていた。
「来たよ!」
階下から野山君が叫んだ。
「トラックが横付けだ!どこへ連れて行くのだろう」
窓のすき聞からのぞいた大久保君が眼を丸くして皆んなをかえりみた。われわれはすばやく身辺を整理して、紙幣は靴下の中へ入れたり、上衣のえりの中へ縫い込んだりそれぞれ強盗防ぎょ対策を講じた。
やがて……警備兵五名。白系の通訳が先頭に立っている。
「あなた達は軍人ですか、地方民ですか?」
抑留生活(一)
われわれは中庭へ整列してから所持品の点検を受け、めぼしい物は没収せられた。
ズボンまで脱がされている者もあった。
(どこへ連れて行かれるのだろうか、地方民を偽装しているため銃殺されるのではなかろうか)
われわれは終局のことを想像した。
垣の外から満人、白系ロシヤ人が珍しそうに眺めている。その中には李さんも混ざっていた。われわれが警備兵に護衛されて出発するや白系ロシヤ人が潮のように宿舎に押寄せた。全く火事場ドロ棒そのままの図である。
自動車はソ軍警備隊司令部前で停止し、裏の簡易収容所へ連行せられ再び服装検査が行われて、用意してあった二枚の下着と靴下は、それぞれ一枚を没収せられてしまった。何もかもただ一枚きりになって、やがて襲い来る朔風に戦りつさえ覚えた。ソ軍の上級中尉が無言のまま現れて一同をへいげいし、何かしら兵に命じているようだった。すぐ収容所に入れられると既に二、三十名位の日本人がら致されて、無りょうをかこっている。
「あなた達は何時頃連れられて来たのですか?」
私はら致されて、どう処理されるか見当もつかぬので先客の一人に尋ねてみた。
「昨日メイ化から列車で来て、ハルピン駅へ着くなり連行ですよ」
「どこへ連れて行くのでしょう」
不安でならない。
「香坊の満軍兵舎らしいね」
防寒帽をかむった小男が傍からいった。
「野郎ども・・・・・連れて行って何をさせあがるのだ、殺す気か」
「……」
一同は一瞬黙った。司令部の時計が十三時を打った。昼食をとっていないわれわれは急に空腹を感じた。警備兵が無気味な眼を投げかけて歩いて行く。
バターのにおいが鼻をかすめ、腹の虫がおさまらない。女の兵隊が口笛を吹きながら司令部へ入って行った。そして四時の時計が鳴った。
「畜生!われわれはロシヤに負けたんじゃないぞ」
精かんそうなヒゲ男が怒っている。その時兵隊が入って来た。
「ドパイ・シュダー」
右手で招いた、来いといっているらしい。日本人は全部起立して外へ出た。われわれは一刻も早く行くべきところへ行きたかった。そして落着きたかった。
再び四列に整列させられて人員点呼が終わり、七名の警備兵に護衛せられて香坊へ通ずる大きい道へ出た。
陽は西山に没し雲を真赤に染めている。暮色が白樺に射して淡く投影している。
アカシヤの葉が夕風に舞い落ちた。
飛行場の横を通るころには、とっぶり暮れて視界が分からない。腹が空いて歩行に難渋を極める。
一同ただ黙々と歩くのみ。
(われわれを連れて行ってどうするのだ)
ナゾは依然として解けない。四十分位歩いて香坊が近くなって来た。貨物しようへ行く道を左へ折れ、三百米の小径を南北に入れば満軍兵舎がある。
その角まできた。満軍兵舎は火事にも紛う大火が空に映って赤い。
「日本人を火あぶりにするのだ」
沈黙の中から火を見てだれかがいった。悪いことばかり想像する。
「火葬だ」
暗の中からまた聞えた0無気味な夜である。われわれは「死」を直感した。兵舎は森に囲まれてその中に三、四むね平家がある。そして外では大勢の日本人がたき火をしている。暗の中を右往左往しているように見え、何をしているのか分からない。
(どうするのだろう)
疑惑は依然として去らない。
抑留生活(二)
熱気を帯び大森の中を歩めばフン尿の臭気が鼻を衝く。多くの日本人が飯ゴウを下げて、炊飯しているのを見るとダ液がグッと喉を通って急に空腹を感ずる。
満軍兵舎の前で整列し一応解散した。
(何時だろう・・・・・・)
時計はソ連兵に盗まれて、だれ一人持っている者はない。その時、指揮者らしき日本人がツカツカと寄って来て、
「皆さんご苦労さまでした。私はこの収容所の隊長をやっている者であります。われわれ日本人が毎日狩り集められてここに収容せられているのは、どんな目的のためであるか全然判明しておりません。ソ軍の命を待つより仕方ありません。今夜は狭いところですが、お互いに辛棒していただきたいと思います」
簡単に言い終わると、ヤミに消えて行った。その夜は布団も夕タミも板もない土間に、疲れた身体を互いに体温を交しながら仮寝の夢を結んだ。人のざわめきも次第に消え、夜は更けて行く。どこかでふくろうがないていた。
寒さにふと目覚めて雨戸のすき聞から忍ぶ夜風がせつない思いを深くする。
うらぶれ果てた敗戦日本の抑留者は、今ハルピンの一角で坤吟(しんぎん)している−私は運命の変遷をひとしお強く感じさせられた。
うつし身に耐え忍びてぞますらおの
今日の命を世々に伝えん
またしても胸打つ一句がこみ上げて来る。マブタを閉じて愉しかった昔日のおもかげが走馬燈のように去来し消えて行く。
(ああ異国のはてに生き長らえるこのいのちは何時まで続くのであろうか。今日も生きた、明日は
土に朽ちるか−。)
夜の雲が北から南へ飛んで行く。
雨戸の目張りが忍び風に鳴って震えている。そして−−、同胞のいびきが脳裏にさえて眠れない。
抑留、何という現実か、宿命か。
私はしばらく眠った。一人二人起き出て用足しに行く足音に目覚めた。
戸外にソ連兵と日本人通訳がボソボソ立話しているようだ。すると通訳が、
「各隊から三名あて食糧受領に本部まで来て下さい」
と伝達した。
「おい、朝食くれるのだぞ」
「飯だ!」
「飯だ起きろ」
食欲に餓えた群が交互にいきり立つ。
飯盆音があちらこちらに響いて本部へ押寄せている。私はどんな食事を配給されるのであろうと心待ちにしていると、少量の米飯とみそ汁だった。米飯は一人あて茶碗いっばい位の配給で、驚いたことに、みそ汁は湯に味そを溶かした程度のもので何も入っていない。
私は各人、茶器がないので空かんを拾って作った。箸は木の枝を手で折って作った。
いっぱいの飯では腹の虫が治まらないので、給水で外出の都度、ソ連を通じてトマト、メロン、アンズ等を金の有る限り買って食べた。
それは一時の空腹を満たした。私はこんな毎日が数日も続けば、栄養失調で倒れる者が相当あるものと予測した。
だが、しかし、やがて米が麦に代り、粟が混ぎつて高りゃんになった。抑留者が次第に増加して来ると、主食が高りゃんになり、副食は味そだけとなって来た。
そして次に来る強制労働を思うと矢もタテもたまらなくなった。
(日本人の食糧を次第に減退させて餓死させるのだ)
私は死の恐怖を感じた。こんな毎日が三日過ぎたあるたそがれ、本部から伝令が来たので私が受
け取った。回覧板である。
(伝 達)
「今夜七時三十分より胞人十三名の火葬を行うから、各隊より一名あて本部へ派遣せられたい。本部」
私はがく然とした。胞人の火葬・・・・・死因・・・・・栄養失調?
私の脳裏には通り魔のように不吉な予感がかすめた。私は本部へ赴いた。
本部委員らしき人で長身の協和服が現われて、
「皆さん回覧でお知らせした通り、今夜七時三十分より向こうの鉄道線路の南側で、現在抑留されている胞人の犠牲者十三名の火葬を行うようソ連当局より指令がありました。お気の毒ですがよろしく お願い致します」
と簡単に要旨を述べた。
私は協和服の男の言葉を一ツ一ツ聞きとっていたが、
「ちょっとお尋ね致します、死亡の原因は?」
私はその答を待った。
「発疹チフスと栄養失調です」
男は無造作に答えた。
やがて石油と薪が用意されて、死体の両脇に積重ねた白樺に点火し、石油が撒かれてドット燃えた。人生の終えんである。異国の地で他界した無罪の人達は煙と共に昇天して行くのである。
ああ哀れ−燃える臓ふを白樺で返す同胞の手は震えていた。この火葬をさっきから木蔭でながめていた一人の老人は、子供のように泣き叫んだ。その声に一同は感涙をさそった。
火葬は五時間位して終わった。栄養失調は毎日のように激増して行ったが、防疫する医療材料もなければ医師もいない。われわれの身体は刻一刻と衰弱して行く。
ら致、抑留、餓、暗澹(たん)たる将来がひしひしと胸に迫る思いがした。
その翌日・・・ソ連の指令があって、香坊開拓訓練所へ移住することとなり、警備兵に護衛されてここから二キロ南方の地点へ出発した。その日その日が割切れない思いで何の希望もなく生き長らえる捕虜生活、その中に郷愁のみが思索を支配する。毛布を背負う者、手拭でホホかむりして歩く者、長蛇の列を物珍しそうにながめる満人の群ヨホコリと砂煙の中を長駆二時間、漸く訓練所に到着した。
正面には哈爾浜(ハルピン)開拓訓練所と書いてある。落伍者が到着してから各宿舎に割当られ、われわれは第三中隊に入ると、
「おや!」
一同は疑惑の眼をみはった。女性の姿が見えるではないか。
「貴女達はどこから来られたのですか」
物好きな益村君が坊主になった婦人に尋ねた。
「はあ、弥栄開拓団の者です。南下したものの鉄道は通じないし仕方なくここへ参りました」
みすぽらしい開拓団員である。みんな断髪している。
「そして食事などは?」
「ソ連から少量配給されますが到底足りませんわ」
「何時から入所しているのです?」
「終戦後すぐだったのですが、何しろ地理が全然分からないものですから」
彼女達は生命と財産のみは保障されてソ連兵に警備されていた。
宿舎の周囲は雑草が生い繁って見とおしがきかない。
われわれはこの埋れた土地で何をさせられるのであろうか?。それのみが不可解である。
漸く各部屋に落着き、洗濯する者、裸で冷水を浴びる者、シラミをとる卦など解放された人間の裸像が各所に展開された。
「満里兵舎より大分良い。三等寝台位かな」
空腹と疲労で、さすがの大久保君も大の字に寝そべって、この新天地にくつろいだ。
やがて一同は睡魔に襲われ深い眠りに落ちて行った。舎前のアカシヤが夕日を浴びて、大地に大きく影を投げかけている。
私はこの数日が、長い過去のように思われて仕方なかった。それもそのはず、捕虜というかつてない苦しい試練のとりこになっているからだった。
抑留生活(三)
ここはハルピン市外の街はずれ・・・・・大陸の田園の中に建築された訓練所で、かなり古い建物
ではあるが、戦時中は相当数の銃器を装備した少年部隊が屯(たむろ)していた。
われわれが宿舎に入ったころは、もはや開拓団も解散され、銃器はそのままソ連に接収されて、少年達は既に南下した後だった。
そしてまた翌日・・・・・われわれ抑留者全員が広場へ集合させられ、ベルウォッチ(通訳)を通じてハルピン在住者であった者と他の地区から避難して来た者に二分され、ハルピン市民は即刻香坊駅より牡丹江地区へ連行された。そしてわれわれ避難民はハルピン市内の軍需民需物資や日本人の資産、工場の機械器具などを松花江より船積または貨車積させられることになった。
「いよいよ就労だ、いやソ軍のかっぱらいだよ」
みんなは彼らの非行をののしった。
しかし命令には服従しなければ銃殺だ。
さっき同胞が牡丹江へ出発したと思うと、今度は北からソ軍の兵士を満載した貨車が駅へ到着した。幾十輌も連結した車輌の横べりにはスターリンの大きな肖像画が揚げてあり、兵士は各個に赤旗を振って、コーラスをやっている。私はソ連の合唱を度々耳にした。
ソ連という国民は、一般に牧歌的でミュージカルな性格所有者である。彼等は老いも若きも皆、音律に長けて、手を振り、足を振って戯々として喜ぶ童心のような無邪気さは、愛すべきものであると思った。芸術は国境なしとだれかが言った言葉もむべなるかなと、大陸に育まれた人間ソ連の全ぼうが分かるような気もした。
列車から降りたソ軍はどこかへ消えて、まわりは静寂を取りもどした。大陸は無限の力を持っている。大いなる力と絶間ない胎動を続けているあのチャイコフスキーが奏でた大熱情もまたこんな環境から生れ出たものであろうと思った。戦争や抑留がなかったらパールバックの大地を連想する。
心の平和郷がやっとよみがえっている時、
「集合!」
するとどこからともなく十輪車のトラックが十数台到着した。トラックは全部アメリカ製である。
われわれは警備兵に伴われて分乗し、ハルピン市内を北へばく進した。
私のすぐ横にすわった若いソ連兵は、
「シガレッツ」
といって、一本あて煙草を分配してくれた。
そしてコーラスをやれという。それで「予科練の歌」を始めると、
「ハラショ、ハラショ」(うまい、うまい)
と親指を出してこう笑った。ユーモラスなふん囲気を乗せて一路南京街へ疾駆する。
ハルピン市警察署から北東へ下る坂道まで来ると前方延々と行進するソ軍の隊列を見た。
もはやその先頭は市街の中央部より右折している。示威行進である。トラックは先を臥ばまれて進めない。それで隊列の後尾へ付いた。満人が道路の両側に立並んでじっとながめているが時折、歓呼の嵐につつまれる。
中央部に入るや軍楽隊の奏するリズムに乗って、兵士もろとも入城を迎えた。その後尾につくわれわれ十数台のトラックは依然として進めない。
するとどうであろう・・・・・群集は歓迎どころか、トラックに積まれた日本人に対し、手を挙げ大声を張り上げてちょう笑し始めた。われわれは仕方なく顔を隠した。この侮辱には耐えられない。歯をくいしばり拳を握って辛抱した。だが次々と起こるちょう笑の嵐、中には石を投げる者やタンを吐きかける者などこの世の地獄にまさる時ならぬ衝撃に顔をおおった。
ソ軍が入城に捕りよを従えて来るものと誤察しているのである。
ああ忍従の数刻・・・・・またしてもこみ上げて来る涙、皆んな泣いた。抑留、捕虜とはこんなものだろうか−日本はどうして敗けたのか−私は全身にみなぎる男魂の熱情を涙で制するより仕方なかった。
侮べつの声を浴びて松花江の畔満モウ株式会社に到着した。宿舎に一歩入れば眼も当てられぬ惨状で、住民が戦乱に乗じて日本人家屋を襲った跡が歴然と残っていた。
われわれは、その中を整理し始めた。満足に原形を留めているものはなく、ただ神様、花がるた、ゲタのみが放置されていった。
警備兵はその日から表門を閉め歩哨や動哨を配置して、警戒の任に当たった。
ソ連兵は自動小銃を肩に厳重な監視の網が張られた。
ソ軍は進駐以来、物資輸送隊最高司令にワロージン中佐が任命せられ、捕虜隊長にはナゾロフ中尉が当たり、われわれむその管理下に置かれた。この会社に収容された日本人は七百名程度で中尉の示達により一コ小隊三十名を以って編成され中・大隊に大別され、司令所には若干の本部要員を設置、隊長、通訳、給与、庶務等に区分された。
その日から粗雑な毛布一枚を配給された。部室をやっと整理した連中は、
「青ダタミだ・・・・・香りがするじゃないか」
何カ月も見たことのない夕タミを珍しがった。
「タタミの上で死ねば本望だよ・・・・・だがしかし、明日から強制労働だ」
開拓団員で編成されている弱々しい声が隣から聞えて来た。やっと落着いたと思えば、もう夕やみが流れて、松花江からドラの音が聞えた。取残されたような青いタタミから、各人の命脈に交って名状しがたいノスタルジヤがわいて来た。
その夜は真赤な一ばいの高りゃんと味そ汁を食べ、疲労した身体をタタミに横たえた。外は静かだ。かつてはウソと虚栄でその日を送った大ハルピンも自然の眠りに閉ざされて行った。
ふと、
「裏のヘイから夜に紛れて脱出したら」
私は恐しいことを自分にいい聞かせた。脱出が発見せられて、ソ軍につ卓出されば必ず死刑だということは分かり切っている。
澄み切った脳裏に脱出の二字が浮んでは消えて一閃死刑の文字で否定された。
翌朝就役に際してナゾロフ中尉は田村通訳を通じ、「諸君は本日からソ軍と一緒に神聖なる労働に従事する。労働が終了すれば解放され、自由な身体になって東京ヘダモイするのであるから、私の命に従い、一生懸命働くためのパンを獲得せられたい」
簡単に訓示した。大きい眼がギョロギョロ光って精悍なスラブ族の特徴をみせているナゾロフ中尉は、
「諸君が万一この収容所から逃亡するようなことがあれば、全体の責任において重刑に処せられることを銘記せられたい」
と怒るようなゼスチャで降壇すれば秋林百貨店主(日本人中佐)がわれわれの大隊長として指名された。この人の奥さんは白系ロシヤ人であった。ロシア語もうまい。
作業はいよいよ開始された。
先ず香坊にある関東軍経理部の倉庫から松花江までトラックでワイヤーを運んだ。街を通るたびに、感激の手を振る婦女子の姿も哀れであった。
街の治安もやや落着いたが、日本人封鎖、官公庁の接収、重要人物の監禁は相次いで続出し、殊にハルピン病院における看護婦暴行事件は人間性のかけらもない野獣的な行為で市民を戦りつさせたものだった。
われわれは松花江に出た。ほうはいたる水に陽光が銀波に砕け、江上に平和がよみがえっているように思われた。流れに衣を洗う満人の女。チチハルに通ずる真黒い鉄橋…・折から列車は南満の物資を積載してシベリアヘ行く。
そのシベリアヘ行く貨物列車に日本人捕虜が乗っている。荒れ果てたポロ服に手拭でほおかむりをしているのだ。当方の同胞は列車に向って叫んだ。
「お−い、元気にやれよ!」
抑留生活(四)
運んだ物資を松花江の貨物船に積んだ。三日に一度は徹夜作業を強いられ、中には機械の下積になって両足骨折したもの、伝染病でたおれるものが続出したにも拘らず、
「スカレースカレー」(早く早く)
とまるで牛馬を扱うように酷使された。「労働は神聖なり」という理想論などどこからも見出せない。火事場泥棒的な作業を強制せられ、食事は高リャンと乾燥野菜ばかりで、われわれの身体は衰弱して行くばかりだった。鉄道工場も航空機工場も満拓倉庫へ行って毎日機械、被服を運搬した。
そしてある晩秋の雨の日、銀せんが粛々と降る冷たい小雨の中、何時ものように数台のトラックに運ばれて宿舎へ帰って来た。
ぬか雨にアカシヤはぬれている。手拭で顔をふきながら部屋へ入って行くと、満人が五、六人煙草をふかしながらすわっていた。
(こんなところにどうして満人が?)
私は不思議でならなかった。
「ご苦労さまでした」
われわれが兎るなり流ちょうな日本語で丁寧に挨拶されたので戸惑った。
「はあ雨にやられましてね、全く面食ったですよ」
満人はチェンメンの煙草を一本さし出して、
「まあどうぞ」
「・・・・・」
どうしても解せない満人である。
粋な背広にロシヤ語の腕章を付けて一見宣撫工作員のような服装である。
その中のソバカスの男がちょっと破顔して、
「あなた達現在の仕事は苦しいですか?」
「はあ苦しいけれど敗戦国の身ですから仕方ありませんよ」
私は上衣を脱いでハンガーにつるした。
「とても楽な仕事があるのですが、やってみる気はありませんか?」
私の背を追うように言葉をかけた。彼等は緊張しているようだった。私は敗戦の日本人を使用するのは技術員しかないのに妙な満人だと思ってその言葉を信じなかった。
側で聞いていた益村君が不思議そうに、
「その仕事ってどんなのです?」
眼を丸くして聞いた。
「ハハ・・・・・軍人みたいなものですよ」
男は吸った煙草をすり消しながら、
「ソ軍の指揮下で働く小部隊で、日本人には千円の月給と米食を支給することになっているのです。
日本は友邦ですからね、如何です皆さん」
男は一同を見回して、自信あり気に二ヤリと笑った。
「ソ軍の指揮下って、そんなの許されているのですか?」
不可解な突飛な男の言葉に、今度はリーダーの土橋さんが言葉を入れた。
「簡単にいうと工作隊ですかナ」
「工作隊?」
「はあ」
「・・・・・隊長はだれですか?」
私は隊長を知ればおおむね分かると思った。
「毛沢東先生ですよ‥‥ハハ‥…・分かりましたかな」
男達は満語で何事かしゃべっている。私はかねて 「入路軍」 の組織は知っていた。毛沢東の率いる共産軍だということはだれもが知っていた。
「何れ考えた上で確答致しましょう」
「ナゾロフ中尉にも頼んで置きますから、よく考えておいて下さい。何れまたお伺い致します」
男達は二ヤニヤ笑いながら立去って隣の宿舎へ行った様子だった。入路軍は地下工作をやって共産軍の組織化を急いでいるのだ。そして日本人の弱みにつけ込み、編成運動を起こしていたに違いなかった。
「危ない。あんなところに行ったら日本へ帰れんぞ」
男達が帰った後ケロリと忘れたように笑いに流した。
「ハハ・・・・・」
大久保君は大声を上げて笑いこけている。
「何がおかしいのだ、気でも狂ったんでないのか大久保?」
益村君は、コップ酒を右手に持ってめいていしている大久保君を不思議そうにながめた。
「お前の顔だよ」
「何んだおれの顔がどうしたんだ」
「鏡でも見ろよ」
「顔に何か付いているのか?」
益村君は窓ガラスに自分の顔を映してみた。煙突男みたいにすすけている。
「分かったか?」
「そういうお前の顔を見てみろ、眼の下に眉毛があらぁ」
今日は珍しくも双十節。ナゾロフ中尉の好意で三本の日本酒が配給されたので、各小隊は捕虜の身を忘れて、盛んに気焔を上げている。
街から胡弓の音が混乱の巷を浄化するように流れて来る。満人は陶酔と狂喜乱舞のルツポの中でこの祝日を謳歌しているに違いない。警備隊本部でも、一人の兵士がバルコニーに腰を下してアコーデオンを奏でている。
だれがひいているのか顔すら分からないが、黒い影が淡く異様に動いて、美しいリズムがやみに聞えて来る。バルコニーの下ではロシヤ民謡であろうか、男声コーラスが双十節にふさわしい今宵ひととき、荒むわれわれの心を慰めてくれた。
私は夜の更けるのも知らず、二階の窓から耳を傾けた。そして桃源郷に誘う乙女に、飛び交う蝶につれて、平和が音楽に乗って訪れて来るように思われた。
その時、私は異様な声を耳にした。うめき声・・・・・苦もんの声だ。声は隣の小隊からである。
「病気だ!」
私は苦しそうな病人の断末魔を想像した。
隣の部屋へ人の出入りする気配がした。私はせき立てるようにふすまを開けた。
そこには今食事から帰ったばかりの二、三人が病人のまくら辺を囲んでじっと見守っている。
「どんな病状ですか?」
手ぬぐいで頭を冷やしている二十歳位の男に尋ねた。その男は振返りもせず、
「作業中軽い頭痛だったのですが、帰るとすぐ寝るといって横になったきりこの状態なのです・・・・・。
発シンチフスでしょうかね」
言葉は低く重かった。私は病人の頭に手を遣りながら、
「熱はありますか?」
と問うたもののひどい熱に驚いた。
「三十九度位ですか?」
「そうですね四十度位ありましょうかね」
「ともかくひどい熱病です。何しろさっきからうわ語ばかりしゃべっているので」
「・・・・・」
一瞬沈黙が続いた。
病人は真赤な顔して、分からぬことばかり口ごもっていた。
この小隊は遠くスイ化方面の開拓団一行で東北地方の人々が大部分だった。
「医者も薬もないのだから可哀そうですよ」
病人の顔を見守っていた四十歳位の男が涙をためてつぶやいた。
病人は次第に衰弱して行き、間断なき熱に襲われて顔色も悪く眼球はうるんでくちびるは変色してきた。
「あああ…」
苦しそうに両手で自分の頭髪をかき胸を開いて阿修羅のような苦闘の連続にまくらもとに居並ぶ人びとはただどうする術もない有様。
「ナゾロフ中尉を呼べ!」
だれかがしかるようにいった。伝令に走った後、小康を取りもどしたが瀕面蒼白となり数刻の後、病勢が急変し友人に守られつつ、この世を去って行ったのだった。外にはナゾロフを呼ぶ伝令の声のみが哀れをそそった。
抑留生活(五)
その夜は一同でお通夜を行い、遠く内地に在る遺族のことなど思い浮べ生前、故人の薄幸だった生涯を懇ろに追とうした。
話題が尽きるころ、東雲を赤く染めて白々と夜が明けて来た。
友を一人失い、また二人この世から去って、幾多の犠牲者をわれわれの手で埋葬した。同胞が死んで行くたび、われわれに果せられた重労働と、この世の逆境に涙せざるを得なかった。
それから数刻の後、ナゾロフ中尉から日本の最近のニュースだと言われて、ポツダム宣言受認の実相やミズリー艦の記事をそのままじかに聞かされ、イエシロフ中尉から共産党とはどう言うものかという共産教育を受けさせられた。中尉は神の否定即ち唯物論の真理を具体的に例示してレーニン、マルクス主義を説いた。彼は再三、
「経済の実力を持つ者に権利と自由を与えないから闘争や革命が起こるのだ」
とか、
「戦争は宿命的思想の葛藤である」
といって、客観的状勢に立脚した共産思想を強調していた。
こんな教育が労働の合間を利用して行われたが、われわれは好奇心のほか積極的に探求しようという気概もなければ、実行する心構えもなかった。ただ現在の希求はこの抑留から早く脱出しよう、逃れようと一生懸命だった。
そしてその機会をねらった。
でも脱出は決死的である。あるいは死を逃れることは出来ない。
「ままよ」
人生をみくびった捨ばち的な気持さえわいて来る。毎日のデカダン生活に重労働、ともすれば荒(すさ)んで行く心を敗戦という心の束縛から強い理性でおさえているのだった。
とうとう十一月上旬がやって来た。焼けた自分の顔と、アカギレの手の甲を眺めては、生きた死かばねと同様な現在の抑留が腹立たしかった。
いよいよ朔風が吹いて来た。寒い寒い朔風だ。凍りつくようなレールの軌幅拡張作業、ハンマーを持って旋盤を外す工事、クレーンに乗ってトラックに積み込む危険さ…。
満州の寒さは早や零下二十度に下らんとしている。冬の到来に松花江の船積も河川の結氷のため中止され、陸路輸送に変更されて宿舎を移転せねばならなかった。現在の南京街から香坊にある旧経理部倉庫に移ったのは十一月十日。
こじきのような姿で、ポロポロの満服に身をまとい、作業中に寸暇を利用して作った簡単なリュックサックを背負う捕虜の身。
抑留されて一度の入浴もしないわれわれには首にアカが黒くなり、だれの頚だか見当もつかぬように変形していた。
抑留者は次々と死亡して行く。そして火葬する。私は幾人かの同胞をアカシヤの蔭で焼いた。その都度新しい涙が流れて、激しい郷愁に駆られるのだった。
一人の抑留者が死亡すれば新しい人がら致される。軍人も市民も避難民も区別のない抑留で、組織や秩序のない労働作業だ。街を歩けばら致される不当なソ連のやりかたに憤怒せずにはおられなかった。
今日も南満から来たという日本人がら致されて来た。
「ははあそうですか。奉天もひどいのですね。暴動が起きたときは・・・・・」
私は奉天の話を聞いて驚いた。
「ハルピンヘ来る列車は大丈夫でしたか?」
私は早晩南下せねばならないので奉天にいたという江藤某に尋ねた。
「いや・・・・・途中はさんざんな事件に遭いましたよ。公主領で中共軍に停車を命ぜられて日本人は全部下車させられ、携行品をりゃく奪するという乱暴でね…」
南満の中共軍の乱行を語る江藤某はかつてどこかの満鉄資材課長をやっていたそうだった。服装はとても汚い。
脱 出
高リャンと味そ汁が続いた。そのため栄養失調で倒れて行く者数知れず。だがソ軍は病気で休業すれば荒々しい言葉で、
「働かない者には飯は食わさない」
といって、強制的に就労させられた。栽は重労働に耐えかねて毎日脱出の機会をねらった。
十一月中旬も過ぎて木の葉が街に舞い、白系ロシア人がシェーバーをまとってアカシヤの下を歩く頃、一望千里の荒漠の平野には高リャンの色が黄色に染って来る、そして朔風に沃野の実りがサラサラと鳴っている。
抑留地、香坊収容所の北の周囲は高リヤンが繁り、南は轄(ひら)けて道路に面している。
表門にはかつて共産主義に弾圧されたポーランド人の兵士が歩哨に立っていた。
私はこのポーランド人が好きだった。もう四十歳近い彼は、共産政策に強い反感を抱いていた。
「ソ連は統制のない軍隊で精神は支離滅裂だ。ソ連は近い将来きっと敗戦の憂目に遭う。きっと瓦解だ」
彼は動哨中、日本人にこのようなことをもらしていた。私はポーランド人は自由と平和を愛する人種であるのに、圧政下におかれる現在の国情が哀れでならなかった。ポーランド兵は何時も煙草をくれた。そしてソーセージを買ってくれた。私は親切という文字など今の世からかき消されたのではないかと思っていた矢先に。
(この兵士に頼んで脱出の機会を作ってもらおう)
こんなことも考え始めた。そして二、三日が過ぎたある風の強いたそがれ。
日本人が作業から帰り、ソ連の人員点呼が終わってから各宿舎へ急いだ。
「ご苦労さん」
銃を肩に煙草をくわえたポーランド兵が横を過ぎ去る。彼は微笑を浮べて軽く会しゃくをした。
私は決心した。
(よいチャンスだ。動哨はポーランド兵だ)
私は宿舎に帰って同志を集めた。
「裏の高リャン畑から脱出しよう、そして南満へ下がるのだ」
「でも君」
叶さんは私の決行を否定した。
「南満には皆んなの家族が路頭に迷っているのだぞ。いや餓死しているかもしれない」
はやる気持はもう制することは出来ない。
「脱出はいいが発見されたら銃殺だよ。分かっているな・・・・・それは暴挙というものだよ」
大久保君はゴロリと横になって窓に視線をそらした。
「暴挙?」
「・・・・・危険だな、君子危うきに近よらずだよ、命を粗末にするな、未だ若いんだから」
そんな言葉をよそに満服に身を固めた。
「おれも行く」
「おれもだ」
側でじっと聞いていた野山、富山君が、私の顔を見つめた。
「よしやろう。タイムリーだ」
水筒と雑のうを持った。頭髪は仙人の様に耳をおおっている。
どこかで爆竹が鳴った。私は銃声かと思ってドキッとした。
「裏口から抜けるぞ!高リャン畑を通って河溝街のハルピン兵事部の寮に行くのだ!」
準備は出来た。歩哨の動静を野山君が偵察した。強い風に高リャンが大きく揺れている。
「それ!」
三人は脱兎の如く、高リャンを縫った。力の続く限りひた走りに走った。途中幾度かテン倒して
血の逆流するを覚えた。
「しめた!」
その時ダダダ・・・・・凄しい銃声。
後を追って来る自動小銃の響。展望哨からだ。たそがれの静寂を破って木霊(こだま)した。
ロシア風呂
「あ!」
高りゃんを通じて、弾がヒュウヒュウとうなる。
「がん張れ!」
私は二人を激励した。銃声はまさしく展望哨からであった。しばらくして自動小銃は止んだ。
「あ!助かった!」
私は畑に伏して、しばらく呼吸を取りもどそうとした、野山君、富山君は青い顔して無言のまま
走った。
空には黒い雲が低く垂れ、北から飛んでいる。
風は少し止んだ様子だった。遠く鳥のなく声が聞えて風に消えて行った。
「命拾いだった・・・・・全く」
野山君が真剣な顔してつぶやいた。
「地獄の三丁目だったなぁ富山君」
彼は二コリと笑った。
「さあ行こう。市民に化けて明朝の列車だ」
三人は何食わぬ顔して高りゃん畑を出た。
足が棒のように痛い。市内は手薄になっているようだ。日本人の出店もあちこちに見られて、道行く人びとも楽しそうに談笑を交している。
その街の表情にひきかえ、われわれの身はどうであろうか。脱獄したようなみにくさ。
森を通って表通りに出た。ら致される前日本兵が砲車を引いて走っていた石ダタミの道…。
ほほをなぶる十一月の落葉−私は三カ月前の風物詩ハルピンの姿を胸に描いた。
やがてハルピン兵事部の寮に着いた。
「ただ今…」
厳重に錠を下ろした表戸をたたいた。ややあってけげんな顔をした主婦らしき人が現れた。
「?」
「私ですよ。牡丹江兵事部の」
私は訴えるように女の顔を見つめて言った。
「抑留されていた方々?」
女はしげしげとわれわれの服装をながめた。
「まあ大変だったでしょう」
「しッ!」
私は女の驚て声を警戒してロをおさえた。
女は引き入れるようにして奥の一室に案内してくれた。
「もう大丈夫だ。いくらゲペウ(国境警備隊)が捜したって駄目だろうよなぁ野山君」
「うむ・・・・・」
野山君は二重ガラスのスキ聞から今来た道をしきりに眺めている。
その時、
「皆さん食事の用意が出来ましたよ」
といって、ドアが開いた。そして女は、
「まあよく帰ったわね…苦しかったでしょう。でもシベリアヘ連れて行かれなくて、大助かりよ。さあ食堂へ行きましょ。もやしの油煮が出来ているわ」
独りしゃべって出て行った。
私は窓ガラスに映る自分の姿を眺めて嫌になった。
やがておいしい米飯をきょう応されて、しやばの味がしみじみ分かるような気がした。
それから一時間、近所の床屋へ行って髪を刈り、帰途ロシヤ風呂に入ってみた。
脱衣もそこそこに湯客の眼を逃れるように浴室へ入った。あたたかいシャワーが全身を浄化してくれた。浴室の窓から見える枯木に小鳥が寒い空を眺めてとまっている。
「こんなものこの世にあったか風呂の味」
下手な川柳が口を衝いて出た。野山君がニヤニヤ笑って、
「冬日和捕虜を逃れてロシヤ風呂」
小声で言って、丸い眼をギョロとさせながら周囲を見回した。
風呂を出た頃はすみを流したような冬の夜。
「さあ、今夜はゆっくり眠って明日南下だぞ」
二人を励まして夜道を急いだ。
運命の地
大陸の精が未だ眠りから覚めやらぬ午前四時、アカシヤ繁る街路樹をぬけて中央寺院の裏街道を通った。道路の両側には深い溝がヤミの中にドス黒い。
「ああ死体だ」
野山君が溝の中を指して叫んだ。
「人が死んでいる!」
われわれは無気味な衝撃に、ド肝を抜かれた思いがした。
「死体だ!」
溝の沼に頭をつっ込んで右手は草を握っている。われわれは朝から不吉な物を見せつけられて嫌な思いがした。大陸の野面(のづら)をわたる朝の風は夜気を含んで冷たい。
駅前の大通りへ出た。
遠くシグナルが瞬いている。乗車を待つ人びとがヤミの中を右往左往しているのが、セントポールの灯りに照り出されている。
私は死に直面するような冷厳な感に打たれて、地上の無為な葛藤を憎まざるを得なかった。
駅の方からゴングと汽笛のみがやみを通して聞えて来る。駅へ着いた満人、朝鮮人、ソ連兵の中でケペウらしき者が監視の目を光らせている。
「チーテンフンテンフォーチョ」(奉天行は何時ですか?)
満語で傍の娘に尋ねた、
「ウーテンスーフン、ニーデティマ?」(奉天行は五時十五分です‥・あなたは行くのですか?」
彼女は丁寧に教えてくれた。
「ティラ」(そうです)
わたしはゲペウを警戒しながら答えた。
「リーペンセンザイブーホウ」(日本人は危険ですよ)
女はジロジロとながめて気持が悪い。アクセントの違う片言まじりに日本人だと感づかれた。待合室は次第に雑踏して来た。
三人は東方陸橋の右側のこう配を下り、貨物列車に飛び乗るより仕方ないと思って駅を出た。
夜のとばりは暁に明けて来る。列車は発車信号を待った。われわれは構内の堤に隠れて片づをのんで待期した。
やがてシグナルが青になって列車は汽笛一声始動した。構内にソ連兵が三々五々警戒に当たっている。列車はフォームを離れてわれわれの前まで近づいた。
「それ!」
三人同時に身を翻えした。
全神経が腕二本に集中されて無我夢中である。だれも感づかれない。
「貨車の中へ入れ!」
三人は貨車へ飛び込んでうずくまった。
死をとした瞬時の飛び乗りである。列車は南を指しスピードを加えて行く。
名残つきないハルピンの街が数奇な運命を残して次第に遠くなって行くうちに、去り難いきづなに囚われて、自分が犯罪を重ねる脱獄囚のように思われてならない。
速力を増して行く貨車の中は冷たい風がさっとかすめる。地下足袋が冷たくてじっとしていられない。
「おい野山君」
「… …」
肩をたたいたが返事がない。
「どうしたんだ野山」
彼は眠っているのだった。ホッと胸を撫で下ろすと列車はホームに滑り込んだ。
「客車に乗ろう。寒くって凍死するぞ!」
野山君を起こしてホームヘ飛び下り、後の客車へ乗客に紛れて乗った。
「ハハ …ティンホ」 (よかったな)
互いに笑を交した。
もう安全だ−と一つのボックスをしめてすわった、前の座席には五、六歳の子供が座っていた。
「ショウハイチーソイヤ」(坊や幾つ?)
無心に遊ぶ子供に尋ねた。
「おじさん何?」
満人かと思ったら、日本人の子供だった。
「坊や幾つだい…」
と尋ねて思わず自分の声にびっくりして周りを警戒した。
坊やと思ったのにどうも女の子らしい。
「どうして髪をそったの・・・・・」
私はつれづれなるままに尋ねた。
「おじさん知らないの‥‥虫がつかないからよ」
私はプッと笑った。恐怖と笑いを乗せて一路奉天へ。
駅々には自動小銃を持ったソ連兵が警戒している。日本人は未だ異動が出来ないのだ。
行き交う列車は南満の物資を積んで、シベリアヘ送られて行く。
時々日本軍を積んだ列車が駅に停車して、南下するわれわれの列車を見送っている。
それから五時間位走ったであろうか。新京近い小駅に入る数分前−。公主嶺だろうか。
ダダダ…・
銃撃である。列車は急停車しようと強くブレーキをかけたが惰力でどうすることも出来ない。車内がとっさの事件に混雑して来た。
私は窓に背を当てて座席の下へもぐり込んだ。
銃撃は聞えるが弾痕がない。
「機関銃を撃っているのだ」
そっと身体を上げて窓から前方を見た。乗客は悲鳴と驚がくでひしめき合っている。
車輌が転覆するように動揺する。
「反対側へ下車だ!危い!」
二人を促して窓から飛び下りようとした時、
ガタッガタッガタガタ
物凄い音響と共に機関車が転覆した。
その衝撃に私は窓から投げ出された。
「キャアー」
乗客は悲鳴をあげて雪崩を打つ。
私はヒジと胸部を強打して倒れた。その上へ折重なるように二人三人…・。
やっと我に返ってみると満服が裂かれて、水筒はどこへやら無くなっていた。
前方には機関車が横倒しになり、次の車輌が半倒れになって脱線し、付近の住民があれよこれよと集って来た。
乗客はお互いの無事を祈って、
「命拾いしたよ。危険だった・・・・・。犯人はだれだ」
犯人・・・・・それは八路軍に違いなかった。
八路軍とは南下列車を襲撃して物資をりやく奪する土匪(どひ)のような軍隊であった。
やがてソ軍が二十名ばかりやって来て、転覆現場の調査を開始した。
原因は犬クギの抜取りらしかった。さっきからどこへ行っていたか分からなかった野山君が急に現れて、
「脱線した車輌には、十五、六名の人が銃撃で射殺されているよ」
「それは満人だったか?」
「はっきり分からないが二、三名日本人がいたかもしれない」
「畜生!ひどいことをやりやがる」
私は共産軍の横暴をにくまざるを得なかった。
乗客の中から、
「八路軍、八路軍・・・・・」「バーロビン、バーロビン」
と連呼している者さえあった。
十一月といえば大陸はもはや冬支度が始まりペチカやオンドルが燃えているころだ。
向うの部落にはそれら煙が南へ飛んでいるのがひとしお寒気をそそる。二時間位経過したころ新京からクレーン列車が運ばれ、機関車と車輌が軌道に乗せられた。復旧工事は終わった。
「さあ出発だ」
列車は再び進行し始めた。
しかし乗客は注意深い眼を窓外に遣(や)って戦戦恐恐としている。さらば大地よ・・・・・北満よ。列車は南を指してばく進する。
おわり
Mickey-sonの追記
満州はなんだった?
近代日本は日清戦争(1894〜95)に勝ち、思わぬ収穫として満州を得た。霧独仏の三国干渉を受けていったん手を引くが、日露戦争(1904〜05)で「10万の英霊と20億の国庫の財」といわれる膨大な代償を払った未、再び満州での権益を得た。もはや単なる外地ではなく、感情的には国士になった。
遼東半島先端の大連が頭、そこから延びる満鉄(南満州鉄道)は背骨、満鉄沿線の付属地が胴体。日本から移民がやって来て、新しい文化が発生した。モダンな駅舎、洋風の住宅が建ち、映画館など娯楽施設が整備された。
「皇国日本から外れた左翼、官僚資本主義国としての日本からはみでた右翼の人々も満州を目指し、剰余が流入した。
余ったエネルギーとパワーを受け止める場所であった。日本で残っている人々にとっては、ロマンチックな北方幻想や、修学旅行などツーリズムの対象でもあり、新聞、文学などのメディアを通じてイメージが膨らんでいった。
満州国(32〜45)では、エリートが設計図を描き、ある種、社会主義的な政策を大胆に進めた。満州国総務庁次長だった岸信介はじめ戦後日本の指導層が経験を積んだ。一般人は日本では夢だった中流生活を満州で実現した。また指揮者の小澤征爾ら満州出身の文化人は相当数に上る。
満州族が建てた帝国 清(1912年滅亡)からみればそれは父祖の地「関東」だった。1920年代には中央の統制が利かない地方「東北」として、張作霖親子の近代化政策の舞台に。そして満州事変がおき、満州国の創設。「植民地としての満州」が現れた。
帝国時代の中国では国土の全体像があいまいだったが満州事変によって、現在のものに近い国土意識が誕生した。ナショナサズムの始まりを画する出来事だった。
近代的鉱工業、農業などが満州で発達した。そこで教育を受けた中国人からエリート層、指導層が出たのも事実。それらはあくまで植民地の、括弧付きの「遺産」だが、「評価はともかく、何があったのか。中国側がどう消化し受け止めたか。ポストコロニアリズムの中で大きな課題だ。
軍隊組織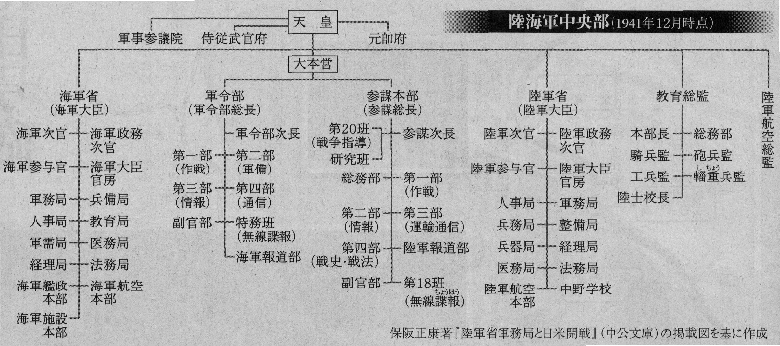
陸軍組織
天皇→総軍→方面軍→軍→師団→連隊→大隊→中隊→小隊→分隊
┗独立混成旅団→独立歩兵大隊