
 At The Meridian Town Akashi
At The Meridian Town Akashi ホーム→子午線情報

 At The Meridian Town Akashi
At The Meridian Town Akashi 子午線の町で有名な明石は由緒ある城下町。初代城主の小笠原忠政が1619年に築いた明石城の跡は、明石駅から歩いてすぐの明石公園内にある。天守閣はもともとないが、東西の櫓は国の重要文化財に指定されている。城下町の線引きを行ったのは、当時、姫路藩の客臣だった宮本武蔵と伝えられる。
「源氏物語」にまつわる史跡も多い。山陽電鉄西新町駅で下車、徒歩10分の所には、光源氏が月見をしたといわれる無量光寺や明石の君の館への通い道だったとされる「蔦の細道」などがある。
切り立った崖が続き、風光明美なことで有名な屏風ヶ浦海岸は、JR大久保駅で下車、タクシーで約10分。旧石器時代とされる「明石原人」の骨が発見された地でもある。
1919年11月1日、兵庫県で4番目の市制施行で明石市誕生。
目次
| 子午線について | 天文科学館 | 子午線モニュメント | 日時計 |
| 明石の魚 | 明石焼き | 明石城 | 山陽道(西国街道) |
| 明石海峡大橋 | 大鳴門橋 |
![]()
中国では、古い時代から図のように方位や時刻を十二支で表していた。方位については、真北を「子」(ね)、真南を「午」(うま)と呼んでいた。子午線とは「子」と「午」の方角、つまり真北と真南を結んだ線という意味である。子午線は、任意の地点を通る南北線のことであり、無数に存在する。明石を「子午線のまち」というのは、日本標準時の基準となる東経135度子午線が明石を通過しているからである。
しかし北海道から沖縄までは1時間20分のずれがある。
 明治17年、アメリカのワシントンで開催された「本初子午線並計時法万国公会」で、イギリスのグリニッジ天文台を通る子午線を世界の経度と時刻の基準となる本初子午線とし、そこから経度が15度へだたるごとに1時間ずつ時差を持つ時刻を世界の各国が使用することが決まった。日本でも、この決議に基づき明治19年7月12日、勅令第51号で明石を通る東経135度子午線上の地方時が日本標準時として制定された。そして、明治21年1月1日の午前0時0分に内務省地理局観象台から全国の電信局に通報され、日本の標準時が使用され始めた。この時から人々の暮らしのなかで明石の地方時が日本全国の標準時となった。
明治17年、アメリカのワシントンで開催された「本初子午線並計時法万国公会」で、イギリスのグリニッジ天文台を通る子午線を世界の経度と時刻の基準となる本初子午線とし、そこから経度が15度へだたるごとに1時間ずつ時差を持つ時刻を世界の各国が使用することが決まった。日本でも、この決議に基づき明治19年7月12日、勅令第51号で明石を通る東経135度子午線上の地方時が日本標準時として制定された。そして、明治21年1月1日の午前0時0分に内務省地理局観象台から全国の電信局に通報され、日本の標準時が使用され始めた。この時から人々の暮らしのなかで明石の地方時が日本全国の標準時となった。
日本標準時子午線の重要性を認識した旧明石郡小学校の校長会の人々が、子午線通過地点に標識を建てることを計画した。同計画に賛同した小学校教員が費用を負担し、東経135度子午線が通る5市11町に先駆け、明治43年10月に石の子午線標識を相生町(現在の天文町2丁目)に建設した。
昭和3年、子午線標識を正確な位置に建て替える運動が起こった。測量を依頼された京都大学地球物理学教室の野満隆治博士は、天体測量に基づく天文経度に標識を建てるべきと考え、明石中学校(現在の明石高等学校」で天体観測を行った。観測の結果、石の標識は103メートル西に寄っていることが分かり、石の標識を相生町巡査駐在所前に移動させるとともに昭和5年、月照寺の正面に新しい子午線標識を建てた。新しい標識は、高さ7メートルの鉄柱の上に地球を形どったカゴ状の球が載っており、その上には日本の異名(あきつ島)を象徴したトンボ(あきつ)が真南に向かって取り付けられた。トンボの標識の建設費は1192円55銭で、その費用の約半分は県立明石中学枚、市立高等女学校、明石女子師範学校、人丸小学校、明石小学校、大観小学校の児童・生徒と教員の寄付によるものであった。
第二次世界大戦でトンボの子午線標識も戦禍を受けた。昭和25年、市民は子午線標識の復旧とともに規模の大きな標識を建設しょうと、県知事を総裁、市長を会長とする「日本中央標準時子午線標識建設期成会」を結成した。また、その建設位置も再度天体観測で決めることになった。観測は昭和26年、月照寺境内で京都大学地球物理学教室の上田穣博士の指導のもと実施され、その結果、当時のトンボの標識から11.1メートル東に正確な東経135度子午線が通過していることが分かった。なお、トンボの標識は昭和31年、現在の位置に移設された。
今までは日本独自の基準(日本測地系)で表示してきたが、平成14年に世界共通の国際基準(世界測地系)に変わり、日本標準時子午線も約250メートル東にずれた。
| 世界測地系 | 日本測地系 | |
| (GRS80楕円体) | (Bessell楕円体) | |
| 明石市立天文科学館の位置 | 135°00' 04.7"E | 135°00' 14.7"E |
| 34°38' 58.1"N | 34°38' 46.4"N |
昭和33年11月7日、市議会に議案第100号「明石市立天文科学館設置のこと」が提案され、同年12月2日に可決された。 翌年4月10日、起工式が挙行され、昭和35(西暦1960)年6月10日の「時の記念日」に子午線標識を兼ねた約54メートルの展望塔と直径20メートルのドームを持つ天文科学館が誕生した。開館から現在までの60年の間に、天文知識を学ぶ生涯学習施設として、そして理科学習の場として多くの人々が同科学館を訪れている。また、塔頂にある直径6.2メートルの大時計はいつも正確な時を刻み、「時のまち明石」 のシンボルとして市民に親しまれている。
明石天文科学館の日本一古いプラネタリューム
経度緯度には2つの種類があります。1つは、それぞれ任意の地点で天体を観測して決める天文経緯度と、もう1つはある地点を天体の観測で天文経緯度を定め、そこを地図の原点とし、地上の測量によって決める測地経緯度です。測地経緯度では、地球が完全な楕円体でなく、しかも凹凸があり、また地下の密度分布が一様でないため、測量結果にはどうしても誤差が生じます。地図の東経135度子午線は、地上測量で決めているのに対し、天文科学館の位置は天体観測で決めています。測量方法が異なるため、現在地図の東経135度子午線は、天文科学館の西約400メートルを通っています。なお、2002年4月より地図はGPS(人工衛星)を利用した世界測地経緯度が導入されています。
日時計の示す時刻(真大陽時)と私たちが日常使っている時刻(平均太陽時)には、少し差(均時差)があります。東経135度子午線上の日時計では、日時計の示す時刻にこの均時差の修正を加えるだけで日本標準時を知ることができます。天文科学館4階の日時計広場には直径8メートルの人間日時計があります。均時差も人の立つ位置で修正でき、簡単に日本標準時を知ることができます。
地上から47.5メートルの高さにある現在の天文科学館の塔時計は3代目に当たります。文字盤の直径は6.2メートル、長針の長さ3.2メートル、短針の長さは2.2メートルで、時計の重さは約4トンあります。 郵政省通信総合研究所とテレホンJJY(日本標準電波)で結ばれた親時計が塔時計を動かしており、その精度は100分の1秒以下であります。 なお初代の塔時計は、開館当時から昭和53年12月までの18年間、2台目の塔時計は平成8年10月までの18年間、正確な時を刻み続けてきました。3代目の塔時計は平成10年1月17日午前5時46分から市民に時を告げています。
6月10日は時の記念日。西暦671年の6月10日、天智天皇が初めて漏刻(水時計)を新台に置き、鐘鼓を打って、人々に時を知らせたという故事にちなんで、大正9年に6月10日を「時の記念日」と制定されました。
以上、出典 明石市政便りより
問い合わせ先 明石天文科学館 Tel 078-919-5000
東経135度日本標準時子午線の真上に建つ明石市立天文科学館は、国内で最も古いプラネタリウムと展示物を通して「天文」と「時」を学ぶことができる施設である。
見学のポイントは3つ。地上54mの子午線塔の13・14階展望室では足元まである大きなガラス窓より見下ろす淡路島や瀬戸内海、明石海峡が絶景である。自然とそっくりに星空が投影されるプラネタリウムでは、四季の星座や惑星の動き、日食や月食のようすなどいろいろな天体現象を体感できる。
そして2、3階の展示室では子午線上に建つ施設らしい「時」と「暦」に関する展示物をはじめ、「天文」に関する展示が充実。宇宙のロマンを感じることができる。 またこれら一般投影や常設展のほかに特別展や観望会なども開催している。
またこれら一般投影や常設展のほかに特別展や観望会なども開催している。
天文館の裏には学問の神様である在原業平ゆかりの柿ノ本神社、1618年小笠原忠政が徳川秀忠から伏見城薬医門から拝領した明石城の切手門を移設した山門がある月照寺があり、松尾芭蕉が読んだ俳句「蛸壺やはかなき夢を夏の月」の句碑がある。
| 明石市内 | ||
 |
 山陽電車高架に記された子午線 N34.647 E135.001 |
 明石検察庁の子午線 N34.645 E135.000 |
| ④トンボの標識 旧子午線と明石市立天文科学館 | ||
 |
 |
|
| 天文町交番所東側の大日本中央標準柱 N34.645 E135.001 |
天文町交番所の表札 | 人丸花壇入り口の子午線 N34.644 E135.001 |
 |
 |
 |
| 明石子午線郵便局前の標柱 | 明石子午線郵便局駐車場の子午線 N34.646 E135.001 |
明石子午線郵便局前の子午線標柱 |
 |
数字はGPS(世界測地経緯度)での測定値 | |
| 「中崎公会堂」南側にある「刻」モニュメント N34.643 E135.001 |
大蔵海岸遊歩道上にある子午線マーク N34.6429 E135.002 |
|
| 明石市外にある子午線 | ||
 |
 |
 |
| 神戸市西区の春日台小学校内 | 春日台公園山中にある天文測量観測点 | 神戸市西区 オークスクエア西神中央内 |
 神戸市西区の「神出めっこうファーム」内 |
 |
 神戸市西区平野県道83号線沿い 「大日本中央標準時子午線通過地識」 N34.723 E134.995 |
| 「神出中学校」東門にある子午線表示柱 N34.754 E134.997 |
||
 |
 |
 「マックスバリュ恵比須店」駐車場(県道38号沿い) |
| 三木市グリーーンハウス店入り口 (県道22号線沿い) N34.781 E134.998 |
三木市宿原にある子午線塔時計台 | |
 三木市「マックスバリュ恵比須店」前 「大日本中央標準子午線」 (県道38号沿い) N34.799 E 134.997 |
 |
 三木市久留実(県道20号線沿い) 「大日本中央標準子午線」 N34.811 E134.998 |
| 三木小学校内 | ||
加東市三草の国道372号線沿いの看板のみ ”A” |
 |
県道353号線沿いの小野子午線公園 N34.863 E134.997 |
| ”A”の西へ150m地点にある子午線 「日本中央標準子午線」 |
||
 |
 |
 |
| 西脇市 日本のへそ公園にある旧経緯度交差点 | 西脇市 日本のへそ公園にある新経緯度交差点 | 京丹後市 日本中央標準時子午線最北端の塔 |
そんな子午線が通る明石には、町のあちこちにユニークな「日時計」が設置されている。
魚住市民センターにある鳥の翼の部分に文字盤をあしらった「日時計・翼」。石ケ谷公園に設置された天の中心・太陽に向かって光り輝くリングを再現した「日時計・環輝」中西部文化会館の「日時計・空」など点在している。
また、明石城と天文科学館を結ぶ約2キロの「時の道」沿いには
①明石公園内の鎧と槍がアクセントの日時計
②白壁が美しい、明石上ノ丸教会の鐘楼の切り妻屋根の下に壁面に設置された日時計
③月照寺・柿ノ本神社前の日時計は一辺155センチの花こう岩に目盛りが刻まれた水平日時計
④中崎公会堂付近にある日時計
⑤大蔵海岸にある日時計
⑥大蔵海岸 こども広場の日時計はトンネル状の遊具に見えるが、筒の中央に細い隙間があり、筒の部分に落ちる影で時刻を知る仕組み
⑦地方検察庁明石支部の日時計は壁面上部に設置されて、建物を子午線が通り、日時計も子午線上にある
⑧天文科学館4階にある日時計群
⑨明石中央体育館前の日時計
⑩第2神明明石サービスエリアにある日時計はノーモンの長さは6mもあり、その根本の黒い部分は太陽を、そのまわりの白い部分はコロナをイメージいる
⑪魚住市民センターの日時計は鳥のくちばしが指針、広げた翼が目盛り板
⑫二見西部文化会館の日時計は一羽の鳥が飛び立つ姿をイメージ
などが設置されており、おすすめの散策コースである。
 |
 |
 |
|||
| ①明石公園内 兜日時計 |
②上ノ丸教会 壁面日時計 |
③柿ノ本神社前 水平日時計 |
④中崎公会堂 | ⑤大蔵海岸 | ⑥大蔵海岸 こども広場 |
| 下記 |  |
 |
|||
| ⑦地方検察庁明石支部 壁面日時計 |
⑧天文科学館4階 | ⑨中央体育館前 | ⑩明石サービス エリア |
⑪魚住市民 センター |
⑫西部文化会館 |
| 4階にあるガイア日時計 | 4階にある半球型日時計 | 4階にある赤道環型日時計 | 4階にある多面体日時計 |
| 正面玄関横にある漏刻 | |||
明石市外にある日時計
 |
 |
 |
| 神戸市西区 春日台公園内 ポートピア’81で展示したものを移設 135度線のラインが公園内に南に長く伸びている |
神戸市西区神出町 県立神出学園内 ほったらかし? |
神戸市西区の「神出ファームビレッジ」駐車場 設置場所 東経134.98北緯34.42 西に600mずれている |
 |
 |
 |
| 神戸市須磨区名谷公園 | 舞子の苔谷公園内 | SUNDIAL@垂水アウトレット北側 |
 |
 |
|
| 稲美町図書館前 | 三木市グリーンハウス店で子午線の下部に | |
 |
 |
 |
| へそ日時計の丘公園の憩いの日時計 | へそ日時計の丘公園の憩いの日時計 | 西脇市 日本のへそ公園の旧経緯度交差点 |
 |
 |
|
| 兵庫県立歴史博物館前@姫路 | 揖保川右岸河川敷 |
![]()
明石海峡や林崎沖から播磨灘に広がる「鹿ノ瀬」といった明石市の沖合には、1年を通じて豊富な海の幸が集まる。中でも桜鯛とも呼ばれている高級魚「明石タイ」や庶民的な明石の味「明石タコ」は全国に名の通る水産ブランドである。また、冬場の海苔養殖、春を告げるイカナゴ漁などはあかしの四季を演出する風物詩となっている。
主な漁獲される魚は
イカナゴ、タコ類、イワシ、タチウオ、アジ、カレイ、スズキ、マダイなどである。
明石海峡に「鹿ノ背」と言われる海底が砂地の隆起があり、3月から4月にかけて鹿ノ背に生息する「イカナゴ」の子が明け方に砂の中から一斉に海面に浮き上がってくる。イカナゴ(スズキ目イカナゴ科)の1年魚「新子(シンコ)」である。水面を長い群(玉)となって泳ぐので玉筋魚(イカナゴ)と呼ばれる。取れたては透明であるが時間がたつと白く濁ってくる。イカナゴの代表的な調理は「くぎ煮」。仕上がりが錆びた古釘に似ていることから名付けられた。炊きたてのご飯によく合う。
兵庫県での水揚げは北海道に次いで全国2位。明石や淡路島の魚師は2隻の漁船の間に網を張りこの新子を網ですくい取る(船曳網漁と呼ばれる)。イカナゴの2年以上の魚は「カマスゴ」(明石ではふるせ(古背)と呼ぶ)と呼び、あぶってポン酢で食べると非常に美味しい酒のさかなである。
※新子
関西では0歳魚を新子、1歳以上はフルセと呼ぶ。寿命は、瀬戸内では3、4年。1歳から産卵する。3歳魚は1歳魚の10倍は産むという。
産卵は水温が13度前後に下がる12月中旬から翌年1月上旬にかけてで、産卵場は水深30mまで。タマゴは海底の砂に付着し、10日から2週間でかえる。稚魚は体長0.4~0.5cm。播磨灘の産卵場としては淡路島、北淡町沖の「鹿の瀬」 「室津の瀬」が知られている。漁は4月まで続く。
新子の豊漁、不漁は色々な条件に左右される。季節風は水温を下げ、アジやカタクチイワシなど新子をエサにする魚も大阪湾から姿を消す。新子は、動物プランクトンのタマゴや幼生を食べるが、季節風でそのエサが河口から沖に運ばれ、新子にとってはエサが豊富になる。
ふるせの存在は、産卵量だけでなく、育つ稚魚の数にも影響する。産卵場からあまり動かない親はエサが不足すると、子を捕食するからである。稚魚が産卵場を離れるとその危険は減る。小さな稚魚が産卵場を離れるには北西の季節風の力を借りなければならない。
明石海峡で採れた魚を売っている通りを「魚の棚」という。明石駅の南(国道2号線南30m)にあり、昔、鮮魚商 が店の軒先に板をしき、その上にずらりと魚を並べた所からこの名前が付いたという。400年前から続く全国でも有数の歴史の長い市場である。鯛、たこ、あなごなど生き魚だけでなく揚げ物、焼き物、干し物も売っている。
が店の軒先に板をしき、その上にずらりと魚を並べた所からこの名前が付いたという。400年前から続く全国でも有数の歴史の長い市場である。鯛、たこ、あなごなど生き魚だけでなく揚げ物、焼き物、干し物も売っている。
JR山陽線明石駅下車、魚の棚まで徒歩4分。たいていの店は午前10時ごろから午後6時ごろまで営業。休業日は店によって違うので要確認。「午網(ひるあみ)」は午後1~3時ごろがピーク。周辺に駐車場あり。
材料(4人分)・・・イカナゴ 1Kg、土しょうが 20~50g、しょうゆ 150cc、さしみしょうゆ 50cc、みりん 150cc、酒 50cc、ざらめ砂糖250g
作り方・・・①イカナゴをさっと洗い、ざるに上げて水気を切る。 ②土しょうがを千切りにする。 ③鍋にしょうゆ、ざらめ砂糖、日本酒、みりんなどの調味料を入れ、煮立てる。 ④イカナゴを固まらないように振り入れ、土しょうがも加える。 ⑤アルミホイルで作った落としぷたをして、ふきこぼれない程度に強火で煮る。煮汁が少なくなってきたら中火で5分、弱火で5分。 ⑥鍋をゆすって煮汁をからめれば火を止める。

明石海峡を挟んで東に大阪湾、西に播磨灘が広がり、潮の流れが速いうえ、プランクトンや餌が豊富。「漁場としては最高」と折り紙がつく。なかでもタイやタコは「明石ブランド」で全国に名をはせる。タコは麦の収穫期の初夏から夏にかけて旬を迎える。「明石のタコは立って歩く」と言われるほど、身がしまっている。潮の流れが速く、えさも豊富で、瀬戸内海切っての好漁場に挙げられる「鹿ノ瀬」で育つ。 調理が簡単で漁獲量も多かったタコは、江戸時代から庶民の食べ物として親しまれていた。
(干しタコ)
干しダコは大量に揚がったタコの処理として作られるようになったという。保存食として重宝され、タコ飯や酒の肴(さかな)として食べ継がれてきた。
タコの墨袋と内臓を除き、頭には竹を曲げて差し込み、足の付け根に切り込みを入れてのれん状に広げ、棒で固定する。夜露にぬれないよう、夕方取り込み、翌朝また干す。この作業を重ねていくと、透明がかった褐色になる。
(タコの刺身)
(タコのゆで方)
※1匹丸ごとではなく分割するのは、ゆで上がりを均等にするため。ゆで上げたタコは酢の物やサラダ、から揚げなどいろいろな料理に使える。生ダコは皮をはいで刺し身にし、皮(吸盤)は湯引きして酢の物にもできる。そのまま焼いてもおいしい。
(タコ飯)
※ゆでダコを好きな大きさに切り、蒸らしの時に加えるとタコの食感も楽しめる。

地元明石では「玉子焼」と親しまれる名物。市内で明石焼を扱う飲食店は、数百店に上るといわれている。季節を問わず、手軽に、まろやかな風味が味わえる明石焼は、まさに市民の味である。
タコ焼のように見えるけれど、ダシにつけて食べてみるとふんわりと柔らかく、中には大ぶりに切られたタコが…。これが明石の粉もん。
ところで呼び方は「明石焼」?「玉子焼」?いったいどちらが正しい名前なのであろうか。
大正の初め頃、浜国道(現県道明石高砂線)の明石川東岸付近の屋台が「玉子焼」として売りだし、作家の椎名麟三氏や稲垣足穂氏、芸人のミヤコ蝶々さんらにも愛された記録が残っている。ですから正しくは「玉子焼」である。地元以外では明石の名物ということから「明石焼」と呼ばれることが多く、明石をPRするということで観光客の方々には「明石焼」とご紹介している。
明石焼は、いつ、どのようにして生まれたのであろうか。江戸末期の天保の頃に誕生したと伝えられている。謎に迫る起源説の一つに次のような話が伝わっている。
一人のべっ甲細工師が、懐に入れていた玉子が割れ白身が固まっていたのをヒントに、白身を接着剤代わりに使い硝石を囲める「明石玉」を発案。この明石玉、珊瑚の代用品として明石の地場産業だったかんざしや掛け軸の風鎮などに使われるようになり、明治、大正期には明石の重要産業の一つとなった。こうして白身が重宝がられる一方、黄身はといえば・・ 大量に余った黄身を飽きないように、きっといろんな食べ方が試みられたのでろう。
そんな中で、明石沖でたくさんとれるタコが、余った黄身と量、味の両方でピッタリ合ったのである。こ うして明石焼が生まれた。明石で「玉子焼き」と呼ばれている明石焼きには、たこ焼きの倍の分量の卵を入れる。
うして明石焼が生まれた。明石で「玉子焼き」と呼ばれている明石焼きには、たこ焼きの倍の分量の卵を入れる。
明石焼きはもともと熱を冷ますために冷たいだし汁で食べていたがやがて熱いだし汁も登場してきた。 明石生まれの「明石焼(玉子焼)」と大阪発祥の「タコ焼」の違いはいろいろあるが、一番の違いは粉もんの命・粉の種類が違うということである。「明石焼(玉子焼)」は小麦粉とじん粉をブレンドして使っている。じん粉というのは浮き粉のことで、加熱しても固くならないのが特徴。粉のブレンド割合はお店ごとの秘密になっているが、「明石焼(玉子焼)」のあのふんわりした食感はたっぶりの玉子とじん粉から生まれると言ってもいいであろう。その他にも、「明石焼(玉子焼)」は中に入れるのがタコだけ。舟に盛らず、上げ板と呼ぶ木の板にのせる。ソースや青ノリ、紅ショウガをかけず、ダシにつけて食べる。焼くのは銅板を打ち出した鍋(型)を使う。などが「タコ焼」とは異なっている。
参考
大阪のタコ焼は、明石焼からヒントを得てできたものだといわれる。
昭和の初めごろ、小麦粉にこんにゃくを入れた「ラジオ焼」という食べ物があった。大阪のあるラジオ焼の店を訪れた客が「明石の方ではこんにゃくの代わりにタコが入っている」と知らせたことがきっかけとなり、アッという間にタコ焼が、大阪中に広がったといわれている。明石焼がタコ焼のまねをした、と思っている人も結構いるのではないだろうか。
お勧め明石焼きの店
大久保町:幸楽、一休

戦国時代、船上町辺り(現在の明石城より南西約1km程の所にあった)に船上城と呼ばれる平城あった。その城に大阪夏の陣の功により、元和三年(1617)、信州松本城から小笠原忠真(ただざね)が入城。
元和四年(1618)徳川二代将軍秀忠が、西国諸藩に対する備えとして、藩主忠真に新城の築城を命じたことに始まる。秀忠は姫路城主であった本多忠政の指導を受けるよう命じ、3力所の築城候補地をあげ、現在の地が選ばれた。幕府は普請費用として銀壱千貫目(時価31億円程度)を与え、3名の普請奉行を派遣している。石垣の普請(=現在の土木工事)は元和五年(1619)の正月に始められ、工事は町人請負で行われたとされる。本丸、ニノ丸等の城郭中心の石垣、三ノ丸の石垣、土塁及び周辺の堀の普請が同年八月中旬に終わり、幕府より派遣の普請奉行はその任を終え江戸へ帰参している。幕府直営工事は本丸、ニノ丸、三ノ丸までで、その他の郭の石垣・土塁工事は幕府と小笠原氏の共同工事で行われている。
普請を終え、同年九月から藩主忠真により櫓、御殿、城門、塀などの作事(=現在の建築工事)が始められ、その用材は当時、大名の軍事力を削減する目的で定められた幕府の一国一城令により廃城となった船上城伏見城及び同国の三木城などの資材を用いて建てたとされている。創建当初の坤櫓については次の史料があり、伏見城の建物を幕府からもらい受け、移築されたことを示している。各建物の建築は翌元和六年(1620)四月に完了した。以後、忠真から17代、明治4年の廃藩置県の後、取り壊されるまで、明石城は約250年にわたり存在した。
明石城は豊臣滅亡後の平和時代の築城で、天守台は造られたが始めから天守閣は持たなかった。本丸の四隅には三層の艮(うしとら)・巽(たつみ)・坤(ひつじさる)・乾(いぬい)の各櫓が建てられたが、維新後に壊されて、 現存するのが西南にあたる巽櫓と東南にあたる坤櫓である。共に桃山城と船上城の遺構を移築したものと言われている。いずれも入り母屋造りの三重櫓だが、妻部を南北に向ける坤櫓に対して巽櫓は東西を向き、一直線上に並びながらも棟の方向が全く異なっている。真っ白な羽を広げた鶴が明石海峡を望むように作られ、国の重要文化財に指定されている。
現存するのが西南にあたる巽櫓と東南にあたる坤櫓である。共に桃山城と船上城の遺構を移築したものと言われている。いずれも入り母屋造りの三重櫓だが、妻部を南北に向ける坤櫓に対して巽櫓は東西を向き、一直線上に並びながらも棟の方向が全く異なっている。真っ白な羽を広げた鶴が明石海峡を望むように作られ、国の重要文化財に指定されている。
築城当時の明石城は、本丸に御殿を築き、四隅に三重の櫓を配したが、天守台の石垣は築かれたものの、、そこに建物は造られず、すぐ南に立つ坤櫓が天守閣に代わる役割を果たしていたとみられている。そのため、坤櫓は高さ13.6mと隅櫓の中で最も大きく、南面は一層を千鳥破風、二層は唐破風とし、西面は一層に唐破風、二層に千鳥破風を据えるなど各面、各層ごとに異なる趣向が凝らされている。
築城から50年余りの間はめまぐるしく城主が入れ替わったが1682年以降の189年間は松平氏の居城としてようやく落ち着きそのまま明治維新を迎えた。
明石城跡を中心に、面積58.4haの広さを持つ 『県立明石公園』。園内は動植物の豊かな自然にあふれ、人々に四季の訪れを教えてくれる。
明石城の別名は「喜春城」。これは『天子南面貴春』のことわざにある 「貴春」にちなんだもの。「春、-草木が育つよう天子は万物の生育を喜ぶ。城主もこの心で人民に尽くす」の意味だそう。この命牙吹く春、園内至る所に植えられた桜も一斉に咲き始める。その見事さは「さくらの名所100選」にも選ばれるほど。特に 「剛の池」池畔の桜並木には素晴らしいものがある。
正面入口を入ったすぐの所にロボットが時を知らせる太鼓をたたく「とき打ち太鼓」がある。

 明石港旧灯台
明石港旧灯台 明石港の灯台は1657年に明石藩主松平忠国によって舟人の目標とする灯明台として作られたと言われている。 明治以前の「航路標識年表」によれば近畿で4番目に造られた灯台になる。波戸崎(はとぎき)灯台とも呼ばれ、市民の間で親しまれる明石港灯台の姿は、木造で建てられたものから受け継がれている。昭和38年に役目を終えるまで300年以上にわたって明石港を出入りする船の安全を守ってきた。

明石港の西にある岩屋神社は、伊弉諾尊、伊弉冉尊、大日霊尊(天照皇大神)、蛭子尊(ゑべっさん)、素盛鳴尊(ぎおんさん)、月讀尊を御祭神とする神社で、明石城主の氏神さまであった。
岩屋神社は、成務天皇の勅命により淡路島の岩屋より御皇神を御遷になり、東播磨の古大社として古くから崇拝篤く、明石城主の産土神として尊ばれてきた。岩屋神社は、家内安全、商売繁盛、昌招福の神、災厄消除、縁結びの神として知られた古社である。
創建以来、稲爪神社と並んで東播磨地域の古大社として人々の厚い崇拝を受けた。特に明石城の産土神として尊ばれ、例年藩主自らが岩屋神社を参拝していた。1737年(元文2)には藩主・松平直常の世継ぎ松平直純が「鎧始めの儀」の際に当社に参拝し、以後、世継ぎの鎧始めの儀の際には当社への参拝が慣例となった。
岩屋神社の夏大祭海上渡御神事の「おしゃたか舟」は、成務天皇の勅命により、明石浦の名主、前浜6人衆が新造船を造り淡路島の岩屋より神様を赤石の国(明石市)にお迎えする際、船を明石浦の浜に着けることができず、西方の林崎前の赤石(明石の名の起源)のところへ船を着け海難防止と豊漁を祈ったことが始まりと言われている。昔はおしゃたか舟を立ち泳ぎしつつ頭上高く持ち上げ淡路島まで渡っていた。


西暦464年に摂津の国、堺に祭られた住吉大神が藤の枝が流れ着いた所に我を祭れと藤の枝を流し、たどり着いた所が播磨の国、住吉でここに神領地として建立された魚住庄の総鎮守社で由緒ある神社。丸山応挙が書いた絵馬「神馬の図」、石田ゆう汀が書いた「加茂競馬(かものくらべうま)の図」がある。また、「のだ藤」の花で有名。

兵庫県明石市魚住町西岡
牡丹で有名なお寺。牡丹の花の見頃は4月下旬から5月上旬頃

大久保町付近
 |
 |
 |
| 明治天皇御休息所 | 旧山陽道(大久保町付近)風景 | 道標 大久保村道と書かれている? |
 |

国道2号線の明石川橋のたもとより瀬戸内海の海沿いに林崎、藤江、江井ヶ島と続く淡路島を眺めながらの約8Kmのすがすがしいコース。途中に休憩所が4箇所ほど有る。
コース途中の谷八木付近に1931年4月18日に「明石原人」(学名:ニッポナントロブス=アカアシエンシス)の腰骨が砂礫層から発見された場所がある。腰骨は戦時中に消失。現在は金網で囲われているが何の変哲もない海岸段丘である。
その他6~12万年前の木器や石器も「明石原人」発見の西側の場所で発見されている。

明暦3年(1657)、干ばつで苦しんでいた林崎地方の村々(和坂、鳥羽、林、東松江、西松江、藤江)が相談し、明石川の上流から野々池まで掘割(農業用水路)を作り、灌漑用の水を確保しようと村人が農閑期を利用して工事を進め、約1年で完成。今では市民の水源にも利用されている。
林崎掘割渠記碑 (明石市指定文化財) |

2~3月に白、赤、桃色など約1600本の梅が見事に咲き誇り、4月にはソメイヨシノやサトザクラが約500本、 美しく咲き、花見客も訪れる明石市の石ケ谷公園を紹介する。
美しく咲き、花見客も訪れる明石市の石ケ谷公園を紹介する。
JR大久保駅から市バスに乗り中央体育館前で下車。同公園は、カルチャーパークとして起伏に富む約16㌶の敷地を約9年かけて整備した総合公園である。中心に建つ中央体育館では、バレーボールやバスケットボール、卓球などを楽しむことができ、更衣室やシャワー室、レストランなどの設備もあり、広く市民に利用されている。
駐車場の入り口近くから入っていき、まず目に止まるのが弾むように軽い走りを見せる馬たち。園内にある明石乗馬クラブでの乗馬風景を眺め、優雅な気分に!①明石乗馬協会(TELO78-935-8900)ポ ニーに乗ることもできる(2周300円)ほか、お試し体験やライセンス取得を目指すコースのレッスンもある。 そこから
ニーに乗ることもできる(2周300円)ほか、お試し体験やライセンス取得を目指すコースのレッスンもある。 そこから 伸びる道を進むと左手には赤い屋根の厩舎と放牧された牛たちがいる。②明石中央体育会館(TELO78-936-6621)を背にのんびりとした、かわいい表情を見せてくれた牛たち…こちらまでのどかな気分となる。高原の雰囲気を楽しみながら右手に目をやると目の前に広大な梅林が広がる。開花期には花が放つ香りを楽しめ、圧巻である。2月上旬から咲き始める。③開花期には見応え十分の梅林。早春のさわやかな風とともに良い香が包んでくれる。一角にある中国風あずまや「明錫亭」は、昭和56年に友好都市提携した中国・無錫市と共同建設したものである。
伸びる道を進むと左手には赤い屋根の厩舎と放牧された牛たちがいる。②明石中央体育会館(TELO78-936-6621)を背にのんびりとした、かわいい表情を見せてくれた牛たち…こちらまでのどかな気分となる。高原の雰囲気を楽しみながら右手に目をやると目の前に広大な梅林が広がる。開花期には花が放つ香りを楽しめ、圧巻である。2月上旬から咲き始める。③開花期には見応え十分の梅林。早春のさわやかな風とともに良い香が包んでくれる。一角にある中国風あずまや「明錫亭」は、昭和56年に友好都市提携した中国・無錫市と共同建設したものである。
そこからアドベンチャートリム広場へ。子どもに大人気の遊具がそろい、休日にはたくさんの人たちでにぎわいを見せる。⑤アドベンチャートリム広場。全長50mのローラー滑り台や丸太ジャングルなどの遊具が子どもたちに大人気。同公園は、小さな子どもからお年寄りまで、それぞれの楽しみ方ができる。(無料駐車場の利用は月曜と第3火曜以外の8時30分~21時15分)
公園を出て第2神明高速道路下をくぐり、南に歩いて5分ほどで岩蛇池にであう。7~8世紀にかけて須恵器や瓦を焼いた20基からなる高丘古窯址群が中笠池の西側にある。うち、13基が発掘調査された。高位段丘の斜面を利用し地面を掘り、下から順次焼くのが登り窯。同窯跡はいずれも全長10m余りの半地下式の登り窯であると記されている。この付近は大きな窯業生産地だったようだ。5、7号窯で作られた軒丸瓦は7世紀に奈良県の奥山久米寺に供給され、3号窯から出土したしびは四天王寺のしびに似ている。一見では土肌の斜面にしか見えなかったが、古代、焼き物を生業した人々の姿をここに想像することで、また明石の歴史の重みを感じ取ることができる。
周辺から名所・旧跡を結んだ播磨平野ため池めぐりの道と、明石谷八木川を歩くみちの2つの近幾自然歩道が伸びている。

 |
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
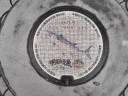 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||


1988年5月1日着工。1998年4月5日年使用開始。
1998年3月27日自転車で明石海峡大橋を自転車で試走できる予定であったが風雨が強く、中止となる。
滅多にない機会であったのに非常に残念。
2003年10月18日に淡路側のケーソンから主塔上に登るイベントに参加した時の写真を一部下記にアップ。
 |
 |
 |
| 海峡幅 Km | 施工箇所の最大水深 m | 基礎周辺の最大潮流速 m/s | 基本風速 m/s |
| 4 | 110 | 4.5 | 46 |
| 橋梁区分 | 形式 | 橋長 m |
支間割 m | 設計基本 風速m/s |
設計震度 | 中央部路面高さ m |
航路高 m |
|
| 吊り橋 | 3径間2ヒンジ 補剛トラス吊り橋 |
3,911 | 960+1,991+960 | 補剛桁 | 塔 | M8.5 | 海面上85 | 最高潮面上 65 |
| 60 | 67 | |||||||
| 塔 ton | ケーブル ton | 補剛桁 ton | 計 ton |
| 46,200 | 57,700 | 89,300 | 193,200 |
| 下方向(40℃車満載時) m | 上方向(0℃) m | 横方向(風速60m/s) m | ケーブル最大張力 ton |
| 約8 | 約5 | 約27 | 62,500 |
| 工費 | 工期 | 延べ労働者数 |
| 5,000億 | 約10年 | 約210万人 |
 |
 |
 |
 |

対岸の淡路の山腹にある温泉。ゆったり身を任せて露天風呂から眺めるレインボーブリッジ(明石海峡大橋)は素晴らしい景観。特に夜間の橋の七色の照明、対岸の灯り、明石海峡を渡る船舶の灯りは一千万ドルの夜景。私のお薦め場所。
場所 淡路津名郡淡路町岩屋3570-77
入浴料 大人 700円 小人400円
営業時間 11:00AM~9:00PM
連絡先 電話 0799-73-2333

 |
 |
門埼(とさき)灯台は瀬戸内海と紀伊水道を結ぶ海上交通の要衝でかつては軍の要塞があり砲台も築かれていた。 |  |
渦の道は、大鳴門橋の橋桁部分に延長約450mの遊歩道を設けたもので、水面からの高さは45m、床の一部もガラス張りになっています。休憩所・展望室の側面や床は一部がガラス張りになっており、迫力ある渦潮の景観を楽しむことができる。
幅1.3Kmの狭い鳴門海峡は潮の満ち引きで瀬戸内海側と外海側に最大1.7mもの落差が生じ、その時に出現するのが渦潮である。特に大潮の時には直径20m以上に達することがある
場所: 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池 Tel 088-683-6262
アクセス: 京阪神方面からは、神戸淡路鳴門自動車道鳴門北ICを降りて、すぐの信号を左折し鳴門公園方面へ。JR鳴門駅からは、市営バス鳴門公園線で約20分。三ノ宮からは高速バスで1時間30分。


 エオの森(野外活動ゾーン)、ミオの森(ふれあいゾーン)、エクウスの森(国際馬事ゾ
エオの森(野外活動ゾーン)、ミオの森(ふれあいゾーン)、エクウスの森(国際馬事ゾ ーン)、いこいの森(産業サービスゾーン)の4つのゾーンから成り立っており、緑豊かな馬とふれあうことができる公園。馬の調教を行っており、馬事センターを中心に馬とふれあい、乗馬の体験もできる。
ーン)、いこいの森(産業サービスゾーン)の4つのゾーンから成り立っており、緑豊かな馬とふれあうことができる公園。馬の調教を行っており、馬事センターを中心に馬とふれあい、乗馬の体験もできる。
宿泊設備及びキャンプ場もある。
場所: 三木市別所町高木 Tel 0794-83-8110

各種申請書がダウンロードできます。
http://www.city.akashi.lg.jp/
相談窓口一覧
県立明石図書館 市立図書館 市民病院 市民会館 県立明石公園
